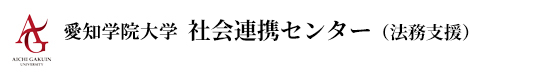量刑問題の検討方法
法科大学院教授 原田保
意見を求められることが時折あるので、私見の一部を記述しておく。司法試験対策の趣旨は全然ない。
1 実務事項
裁判官の量刑判断に対してしばしば「軽すぎる」という非難が行われる。多くの場合、それは被害者(遺族を含む)の意見として主張され、報道機関の支援や一般市民の同調も見られる。そして、「被害者の権利と」いう論理がこれを強化し、裁判員制度による「市民感覚の反映」が「是正手段」と位置付けられて、裁判官のみによる上訴審での量刑破棄に対する非難が行われることもある。しかし、被害者や報道機関・一般市民の見解が正しく、裁判官の判断が誤っている、という絶対的証明が存在する訳ではない。これは概して「視点の相違」なのである。
犯罪類型には殺人罪・傷害致死罪・過失致死罪といった軽重の区別があり、同一類型犯罪でも法定刑に上限~下限の幅がある。故に、量刑に際しては、その犯罪がどれだけ悪いことか、という「程度」の判断を要する。しかし、「悪質度167」といった数値が算出できるものではないから、程度判断の唯一の方法は他との「比較」である。では、何と比較するのか?ここに視点の相違がある。
被害者にとって、犯罪の悪質度は専ら自己の受けた衝撃の程度であり、それは概して自己が過去に経験した衝撃との比較になる。かかる「個人の視点」からすれば、例えば自分の子が殺害されるという事件は、大多数の人にとって、比喩的に言えば「計器の針が振り切れる」ような、計測不能の甚大な衝撃となる筈である。この未曾有の激烈な衝撃に刑という尺度を当て嵌めれば、「最高刑」「極刑」はほぼ必然的な結論である。
しかし、個人にとっては「あり得ない」衝撃を生じる犯罪も、この国で発生する多数事件の中では、往々にして「ありふれた」1件でしかない。如何に甚大な被害感情があっても法定刑を超える量刑はあり得ないし、法定刑の幅は同一犯罪類型の中で「重い事件には重い刑」「軽い事件には軽い刑」という「差」を予定するものである。事件相互に差を付けるならば程度判断における比較対象は他の事件であり、これが「国家の視点」である。殺人罪なら死刑~懲役5年という幅の中で、死刑は上端付近であり、ありふれた事件は中央付近で例えば懲役15年という結論になる。勿論、かかる基準は何処にも明記されていないが、軽重の差を前提とする限り偏りのない分布が求められ、先例との間に軽重逆転を生じる量刑は不合理・不平等である。従って、「あの事件より重い」「この事件と同程度」という比較を要し、このような事件相互の比較に基づく量刑判断の集積が「量刑相場」を形成する。一部には「量刑相場依存」とか「先例追随」とかいった批判的趣旨の表現も見られるが、量刑相場を考慮することは事件相互間の公平性や法的安定性のために必要な事柄であって、決して思考放棄ではない。相場の地域差や時期的変動もあり得るが、大幅・急激だと不公平・不安定になる。
そして、個人・国家の視点選択には刑罰制度の趣旨に関する理解との間連がある。量刑が軽すぎるという趣旨の「刑罰は誰のためにあるのか!?」という批判的問題提起は、これを明示している。犯人への刑罰を被害者のための復讐代行制度と解するならば、当然に「個人の視点」に立って、当該被害者の感覚に基づいた量刑ということになる。しかし、それが現行法の各種規定(典型的には裁判官等が被害者である場合の除斥)や「国家刑罰権」という概念との整合性を持ち得るのか否か、やはり疑問を提起せざるを得ない。現行法の趣旨としては、刑罰を国家としての秩序維持のための制度と位置付ける他なく、「国家の視点」から、この国で起こる事件全体の中での程度に応じた量刑にならざるを得ない。被害者の衝撃は程度判断を行う際に素材の一部たるに留まる。
かようにして、現行法を前提とする限り、大多数の殺人事件で死刑が回避されることは決して不適切ではない。無期懲役を最高刑とする致死罪は性犯罪の場合だけであるから、殆どの死亡事件では有期懲役の範囲で差を付けるしかない。死刑・無期懲役のどちらを選択するべきか微妙な事件で被害者が強く死刑を求める場合に、「復讐代行制度の趣旨を認めた」との外見を回避するために敢えて死刑を回避する、という判断の可能性も否定し難い。
刑罰を被害者のための制度と捉えるのは、被害者への救済・支援を内容とする制度が極めて貧弱であることから生じる刑罰への過剰期待である。被害者の権利を論じると量刑問題から逸れるので、ここでは一言だけにしておく。被害者の権利が犯人への刑罰であるなら、犯人が犯行直後に死亡して責任を負う者が存在しない事件の被害者には、何の権利もないのか?
2 理論事項
量刑問題に関する研究の大多数は、如何なる事情が刑の実質根拠と如何なる関係を有するか、という分析に基づいて、考慮事情および考慮方法を明確化しようとするものである。これは刑罰制度の根幹・適切な刑事司法運営に関わる重要な研究であるが、量刑判断の「法令適合性」が往々にして無視または軽視されていることを指摘せざるを得ない。宣告刑の妥当性という実質論に先立つ法令上の形式論理に、重大な問題が存在するのである。
その典型例は併合罪における刑種選択の方法である。数罪成立の場合の判断方法として、一般論的には「各罪毎の個別判断」と「数罪全体に対する総合判断」との2通りがあり得る(厳密に言えば総合判断の形式で個別判断合計という方法もあり得る)が、如何なる場合にどちらの方法によるべきかについて、しばしば刑法の規定を無視した議論が行われているのである。
数罪成立の場合、量刑作業開始段階では数罪の各々に対する法定刑が併存する数刑の状態である。作業順序としては、判例によれば最初に科刑上1罪処理によってその範囲の数罪に対する刑を1個に纏めるが、この作業を終えた段階ではその他の併合罪に対する刑は依然として各罪毎の刑という数個のままである。この数刑が併合罪処理によって1刑になることがあるが、刑法69条および72条の規定によれば、併合罪処理の前に刑種選択を済ませておかなければならない。そうすると、刑種選択は数罪の各々に対する刑がまだ1個にならず数個併存している段階での作業であるから、その各々に関して選択を行わなければならず、各々についての選択判断であることから論理必然的に、それは各罪1個ずつに対する個別判断でしかあり得ない筈である。
かようにして、法令・判例の指示する作業順序から導かれる刑数の相違の故に、科刑上1罪については最初から1刑になるので一貫して数罪への総合判断、併合罪については併合罪処理の前まで、つまり刑種選択➝再犯加重➝法律上減軽までは、数罪に対する数刑の併存状態だから各罪毎の個別判断、その後の併合罪処理によって1刑になった後の酌量減軽➝量定は数罪への総合判断、という判断方法の相違が論理的帰結となる。これは、個別判断と総合判断とのどちらが適切な宣告刑に到達するか、という実質論とは無関係に、刑法の明文規定から論理必然的に導かれる結論であって、議論の余地すら存在しない筈である。
ところが、判例は併合罪における刑種選択も数罪に対する総合判断によると明言し、学説の大勢はこれを支持している。死刑または無期刑に処する場合の併合罪処理は刑法46条によって他の刑を科さないというものであるが、科されなくなる刑に係る他罪もその死刑・無期刑の処罰対象であるとの理解に基づき、或る罪に関する刑種選択を行う際に他罪への評価を含めて判断する、というのである。数罪数刑の各々に対する個別判断を要する筈の段階で、後の併合罪処理による刑の吸収を見越して、早々と数罪全体に対する総合判断を行うのである。そして、或る罪に関して他罪をも評価対象に含めて重い刑種を選択しながら、既に評価された他罪自体についても刑種を選択するのであるから、他罪に対して2個の刑が導かれ、憲法39条後段で禁止された二重処罰の問題が生じる。
罪の多数を理由に重い刑種を選択することは、罪の程度に応じた刑として大方の支持を得られると推測できる。理論的にも、数罪に対する責任非難が1個である科刑上1罪の場合に数罪総合判断による重い刑種の選択ができるのだから、数罪に対して数個の責任非難が行われて責任非難の総量が増える併合罪の場合に責任非難の総量に応じた重い刑種の選択を行うのは当然だ、との主張は、実質的に適切な宣告刑という観点からすれば十分に説得的である。しかし、その方法は、併合罪処理の前に刑種選択を行うという現行刑法規定の作業順序では、論理的に不可能なのである。併合罪が多数に昇ることを刑種選択に反映させるためには、作業順序に関する規定の改正を要する。
如何に適切な宣告刑に到達する実質論でも、規定上論理的に不可能であれば現行刑法の解釈適用として成立し得ない筈である。それにも拘らず、法令・判例の指定する量刑作業順序から導かれる作業対象刑数と判断方法との関係を指摘する記述は法研会論集20巻1・2号118頁および受験新報684号28頁以外に見当たらず、少なからざる人々がこの点に関する法令適合性を考慮外に置いたまま実質論を展開している。量刑も罪刑法定主義の下にある刑法の適用であるのに、法文を無視して論理的可能性を検討せずに判断方法を提示するという議論が通用するのは何故なのか、全く判らない。
意見を求められることが時折あるので、私見の一部を記述しておく。司法試験対策の趣旨は全然ない。
1 実務事項
裁判官の量刑判断に対してしばしば「軽すぎる」という非難が行われる。多くの場合、それは被害者(遺族を含む)の意見として主張され、報道機関の支援や一般市民の同調も見られる。そして、「被害者の権利と」いう論理がこれを強化し、裁判員制度による「市民感覚の反映」が「是正手段」と位置付けられて、裁判官のみによる上訴審での量刑破棄に対する非難が行われることもある。しかし、被害者や報道機関・一般市民の見解が正しく、裁判官の判断が誤っている、という絶対的証明が存在する訳ではない。これは概して「視点の相違」なのである。
犯罪類型には殺人罪・傷害致死罪・過失致死罪といった軽重の区別があり、同一類型犯罪でも法定刑に上限~下限の幅がある。故に、量刑に際しては、その犯罪がどれだけ悪いことか、という「程度」の判断を要する。しかし、「悪質度167」といった数値が算出できるものではないから、程度判断の唯一の方法は他との「比較」である。では、何と比較するのか?ここに視点の相違がある。
被害者にとって、犯罪の悪質度は専ら自己の受けた衝撃の程度であり、それは概して自己が過去に経験した衝撃との比較になる。かかる「個人の視点」からすれば、例えば自分の子が殺害されるという事件は、大多数の人にとって、比喩的に言えば「計器の針が振り切れる」ような、計測不能の甚大な衝撃となる筈である。この未曾有の激烈な衝撃に刑という尺度を当て嵌めれば、「最高刑」「極刑」はほぼ必然的な結論である。
しかし、個人にとっては「あり得ない」衝撃を生じる犯罪も、この国で発生する多数事件の中では、往々にして「ありふれた」1件でしかない。如何に甚大な被害感情があっても法定刑を超える量刑はあり得ないし、法定刑の幅は同一犯罪類型の中で「重い事件には重い刑」「軽い事件には軽い刑」という「差」を予定するものである。事件相互に差を付けるならば程度判断における比較対象は他の事件であり、これが「国家の視点」である。殺人罪なら死刑~懲役5年という幅の中で、死刑は上端付近であり、ありふれた事件は中央付近で例えば懲役15年という結論になる。勿論、かかる基準は何処にも明記されていないが、軽重の差を前提とする限り偏りのない分布が求められ、先例との間に軽重逆転を生じる量刑は不合理・不平等である。従って、「あの事件より重い」「この事件と同程度」という比較を要し、このような事件相互の比較に基づく量刑判断の集積が「量刑相場」を形成する。一部には「量刑相場依存」とか「先例追随」とかいった批判的趣旨の表現も見られるが、量刑相場を考慮することは事件相互間の公平性や法的安定性のために必要な事柄であって、決して思考放棄ではない。相場の地域差や時期的変動もあり得るが、大幅・急激だと不公平・不安定になる。
そして、個人・国家の視点選択には刑罰制度の趣旨に関する理解との間連がある。量刑が軽すぎるという趣旨の「刑罰は誰のためにあるのか!?」という批判的問題提起は、これを明示している。犯人への刑罰を被害者のための復讐代行制度と解するならば、当然に「個人の視点」に立って、当該被害者の感覚に基づいた量刑ということになる。しかし、それが現行法の各種規定(典型的には裁判官等が被害者である場合の除斥)や「国家刑罰権」という概念との整合性を持ち得るのか否か、やはり疑問を提起せざるを得ない。現行法の趣旨としては、刑罰を国家としての秩序維持のための制度と位置付ける他なく、「国家の視点」から、この国で起こる事件全体の中での程度に応じた量刑にならざるを得ない。被害者の衝撃は程度判断を行う際に素材の一部たるに留まる。
かようにして、現行法を前提とする限り、大多数の殺人事件で死刑が回避されることは決して不適切ではない。無期懲役を最高刑とする致死罪は性犯罪の場合だけであるから、殆どの死亡事件では有期懲役の範囲で差を付けるしかない。死刑・無期懲役のどちらを選択するべきか微妙な事件で被害者が強く死刑を求める場合に、「復讐代行制度の趣旨を認めた」との外見を回避するために敢えて死刑を回避する、という判断の可能性も否定し難い。
刑罰を被害者のための制度と捉えるのは、被害者への救済・支援を内容とする制度が極めて貧弱であることから生じる刑罰への過剰期待である。被害者の権利を論じると量刑問題から逸れるので、ここでは一言だけにしておく。被害者の権利が犯人への刑罰であるなら、犯人が犯行直後に死亡して責任を負う者が存在しない事件の被害者には、何の権利もないのか?
2 理論事項
量刑問題に関する研究の大多数は、如何なる事情が刑の実質根拠と如何なる関係を有するか、という分析に基づいて、考慮事情および考慮方法を明確化しようとするものである。これは刑罰制度の根幹・適切な刑事司法運営に関わる重要な研究であるが、量刑判断の「法令適合性」が往々にして無視または軽視されていることを指摘せざるを得ない。宣告刑の妥当性という実質論に先立つ法令上の形式論理に、重大な問題が存在するのである。
その典型例は併合罪における刑種選択の方法である。数罪成立の場合の判断方法として、一般論的には「各罪毎の個別判断」と「数罪全体に対する総合判断」との2通りがあり得る(厳密に言えば総合判断の形式で個別判断合計という方法もあり得る)が、如何なる場合にどちらの方法によるべきかについて、しばしば刑法の規定を無視した議論が行われているのである。
数罪成立の場合、量刑作業開始段階では数罪の各々に対する法定刑が併存する数刑の状態である。作業順序としては、判例によれば最初に科刑上1罪処理によってその範囲の数罪に対する刑を1個に纏めるが、この作業を終えた段階ではその他の併合罪に対する刑は依然として各罪毎の刑という数個のままである。この数刑が併合罪処理によって1刑になることがあるが、刑法69条および72条の規定によれば、併合罪処理の前に刑種選択を済ませておかなければならない。そうすると、刑種選択は数罪の各々に対する刑がまだ1個にならず数個併存している段階での作業であるから、その各々に関して選択を行わなければならず、各々についての選択判断であることから論理必然的に、それは各罪1個ずつに対する個別判断でしかあり得ない筈である。
かようにして、法令・判例の指示する作業順序から導かれる刑数の相違の故に、科刑上1罪については最初から1刑になるので一貫して数罪への総合判断、併合罪については併合罪処理の前まで、つまり刑種選択➝再犯加重➝法律上減軽までは、数罪に対する数刑の併存状態だから各罪毎の個別判断、その後の併合罪処理によって1刑になった後の酌量減軽➝量定は数罪への総合判断、という判断方法の相違が論理的帰結となる。これは、個別判断と総合判断とのどちらが適切な宣告刑に到達するか、という実質論とは無関係に、刑法の明文規定から論理必然的に導かれる結論であって、議論の余地すら存在しない筈である。
ところが、判例は併合罪における刑種選択も数罪に対する総合判断によると明言し、学説の大勢はこれを支持している。死刑または無期刑に処する場合の併合罪処理は刑法46条によって他の刑を科さないというものであるが、科されなくなる刑に係る他罪もその死刑・無期刑の処罰対象であるとの理解に基づき、或る罪に関する刑種選択を行う際に他罪への評価を含めて判断する、というのである。数罪数刑の各々に対する個別判断を要する筈の段階で、後の併合罪処理による刑の吸収を見越して、早々と数罪全体に対する総合判断を行うのである。そして、或る罪に関して他罪をも評価対象に含めて重い刑種を選択しながら、既に評価された他罪自体についても刑種を選択するのであるから、他罪に対して2個の刑が導かれ、憲法39条後段で禁止された二重処罰の問題が生じる。
罪の多数を理由に重い刑種を選択することは、罪の程度に応じた刑として大方の支持を得られると推測できる。理論的にも、数罪に対する責任非難が1個である科刑上1罪の場合に数罪総合判断による重い刑種の選択ができるのだから、数罪に対して数個の責任非難が行われて責任非難の総量が増える併合罪の場合に責任非難の総量に応じた重い刑種の選択を行うのは当然だ、との主張は、実質的に適切な宣告刑という観点からすれば十分に説得的である。しかし、その方法は、併合罪処理の前に刑種選択を行うという現行刑法規定の作業順序では、論理的に不可能なのである。併合罪が多数に昇ることを刑種選択に反映させるためには、作業順序に関する規定の改正を要する。
如何に適切な宣告刑に到達する実質論でも、規定上論理的に不可能であれば現行刑法の解釈適用として成立し得ない筈である。それにも拘らず、法令・判例の指定する量刑作業順序から導かれる作業対象刑数と判断方法との関係を指摘する記述は法研会論集20巻1・2号118頁および受験新報684号28頁以外に見当たらず、少なからざる人々がこの点に関する法令適合性を考慮外に置いたまま実質論を展開している。量刑も罪刑法定主義の下にある刑法の適用であるのに、法文を無視して論理的可能性を検討せずに判断方法を提示するという議論が通用するのは何故なのか、全く判らない。