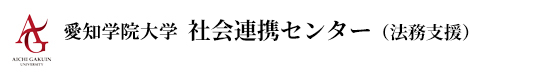脳死の法的意義 [続・完]
愛知学院大学教授 (刑事法) 原田 保
2 臓器移植以外の場面
1で述べた臓器移植法6条1項柱書は移植目的臓器摘出を許容する規定であり、臓器摘出に係る犯罪構成要件が殺人でも死体損壊でも、明文の許容規定があれば法令による行為として刑法35条に基づき適法・無罪になる。しかし、適法評価の実質根拠たる病者救命の優越性を論証する際には、死体損壊の方が説得的である。「含む」が広義概念定義でも擬制でも、脳死体を死体扱いする目的はこの点にあるから、移植目的臓器摘出への法適用以外の場面で同じく扱う必然的理由はない。しかし、かかる規定目的の話では済まない問題が存在する。臓器移植を予定しない脳死体に臓器移植法が適用されないことは当然だとしても、臓器移植を予定する脳死体についても適用範囲の問題は存在する。
それは、死亡診断に伴う効果である。臓器移植法に従って脳死判定が行われたら、同法に基づく死体扱いとして、当該脳死判定日時を死亡日時とする死亡診断書が作成される。この死亡診断書は死亡届に添付されるから、戸籍にも脳死判定日時が死亡日時として記載される。戸籍の記載は、人の生死に関わる基本情報として、民法その他、あらゆる法律関係の前提とされる。その結果として、例えば相続のように臓器移植と無関係な場面にも、臓器移植法に基づく死体扱いの効果が及ぶことになる。この点を看過したまま「臓器移植の場面に限る」と論じるなら、甚だしい欠落である。
つまり、規定目的の範囲に限定して「臓器移植法の効果は移植目的臓器摘出以外に及ばない」と論じるなら、戸籍記載と異なる死亡日時を前提とする法適用の可能性を認めることになる。戸籍の誤記訂正ではなく、同一人の死亡日時を場面毎に使い分けるという話であり、激論になった「2種類の死」問題の一部である。相続に際して死亡日時如何により遺産の行先が異なる場合があることに鑑みれば、深刻な紛争が容易に想起できる。刑法の「お約束」的事例問題では、臓器提供者を殴打して脳死状態に陥らせた犯人の罪責が殺人未遂や傷害に留まるという結論もあり得る。そのような主張・認定が可能なのか、当事者の意思による選択を認めるのか、詳論の余裕はないが、「臓器移植に関する法律だから」という一言は済まない難問である。
3 脳死論争の意義
最後に、脳死に関する論争点や論争理由を確認しておく。
伝統的な三徴候も脳機能の認識方法であり、その意味では昔から脳死を以て死だと理解されていた。現在の脳死は、三徴候に依ることなく脳機能を認識できるようになったことから提示された概念である。脳死否定説も、脳死が個体死だという医学的判断自体を否定している訳ではない。医学的・生物学的に判断された死をそのまま社会的・法的に受け入れることができるのかという問題提起であり、医学的・生物学的な判断だけでは済まない筈だと論じているのである。
臓器移植法に基づく脳死判定でも、法的に要求される2回の判定のうち、どちらの日時を死亡診断書に記載するべきか、という議論があった。判定を2回要求する趣旨は、万一の誤診を想定した用心である。だから、医学的に判断するなら、1回目判定で脳死は確認済であり、2回目判定を以て「1回目判定は正しかった」と確認されたのだから、真実の死亡日時として1回目判定日時を記載するべきだという結論を導き得る。医学界ではこれが有力説だったらしい。しかし、厚生省は2回目判定日時を死亡日時として記載せよという通知を発した。臓器移植法に基づく死体扱いは2回目判定を以て開始されるのだから、同法に基づく死亡診断は2回目判定だという理解である。
また、臓器移植を予定しない脳死体の場合、医学的に脳死だと確実に判断されても、直ちに死亡診断を行うとは限らない。多くの場合、家族は人工心肺器の作動継続を希望する。間違いなく脳死だ、医学的には既に死体だ、と正しく理解していても、復活の期待があり得ない夢想だと判っていても、死体扱いを承諾するには相当の時間を要するのが通常である。だから、家族が患者の死を受け入れるのを待って人工心肺器の電源を切り、心停止を以て死亡診断を行う。
脳死でなくても、同様の事態はままある。素人でも一見明白に死体だと判る場合は別として、心肺停止状態で救急搬送される場合、救急車内で救命士が蘇生措置を執る。既に死亡していて蘇生不可能だと判断できても、救命士は死亡診断の権限を持たない。病院に搬入されたら、医師が引き継ぐ。救命のために搬入されたのだから、無駄だと判っていても、蘇生措置を継続する。それが通常らしいし、家族の心情に鑑みれば、医学や法律を措いても、それが人の道というものだ。そして、相当時間の蘇生措置の後に、やはり蘇生しないと確認してから、死亡診断を行う。真実は数時間前に自宅で死亡したと判断できても、死亡診断書には診断日時に病院で死亡したと記載される。厚生労働省によれば、死亡診断までは「診療継続中の患者とみなす」措置である。
以上の例は、いずれも、医学的に判断される「真実の死」と異なる死亡診断が行われる場面である。医学的な死が直ちに社会的に受け入れられるとは限らない。医学的な死を以て法を適用すると不合理な結論を導くことがある。典型例として、人工心肺器作動その他の蘇生措置は、死体に対する無意味な行為であって医療行為ではなかったことになる。医学的にはその通りだとしても、医療行為でなければ費用は医療保険の対象にならない。如何なる名目で誰がどれだけ負担するのか、かなり厄介な問題が生じる。
このような事態への対応として、医学的には既に死体になったと判断できても、法律上は生体として扱うことがある。医学的な死と異なる死亡診断が、現に行われているのである。
脳死肯定説によれば、これは真実と異なる擬制だということになる。これに対して、脳死否定説によれば、当該死亡診断は社会的・法的に正しく判断された死であることになる。死をそのように社会的・法的な概念として論じるべきだという主張が、脳死否定説なのである。臓器移植法6条3項には、1項の臓器提供意思とは別に、脳死判定に従う意思に関する規定がある。医学的判断と無関係な当事者の意思を脳死判定の要件としていることも、脳死論争の反映である。
賛否は自由に議論すればよい。いずれにしても、脳死否定説に対して「医学の知見を受け入れない頑迷」という誤ったラベルを貼ってはならない。
(完)
(平30・10・15)
2 臓器移植以外の場面
1で述べた臓器移植法6条1項柱書は移植目的臓器摘出を許容する規定であり、臓器摘出に係る犯罪構成要件が殺人でも死体損壊でも、明文の許容規定があれば法令による行為として刑法35条に基づき適法・無罪になる。しかし、適法評価の実質根拠たる病者救命の優越性を論証する際には、死体損壊の方が説得的である。「含む」が広義概念定義でも擬制でも、脳死体を死体扱いする目的はこの点にあるから、移植目的臓器摘出への法適用以外の場面で同じく扱う必然的理由はない。しかし、かかる規定目的の話では済まない問題が存在する。臓器移植を予定しない脳死体に臓器移植法が適用されないことは当然だとしても、臓器移植を予定する脳死体についても適用範囲の問題は存在する。
それは、死亡診断に伴う効果である。臓器移植法に従って脳死判定が行われたら、同法に基づく死体扱いとして、当該脳死判定日時を死亡日時とする死亡診断書が作成される。この死亡診断書は死亡届に添付されるから、戸籍にも脳死判定日時が死亡日時として記載される。戸籍の記載は、人の生死に関わる基本情報として、民法その他、あらゆる法律関係の前提とされる。その結果として、例えば相続のように臓器移植と無関係な場面にも、臓器移植法に基づく死体扱いの効果が及ぶことになる。この点を看過したまま「臓器移植の場面に限る」と論じるなら、甚だしい欠落である。
つまり、規定目的の範囲に限定して「臓器移植法の効果は移植目的臓器摘出以外に及ばない」と論じるなら、戸籍記載と異なる死亡日時を前提とする法適用の可能性を認めることになる。戸籍の誤記訂正ではなく、同一人の死亡日時を場面毎に使い分けるという話であり、激論になった「2種類の死」問題の一部である。相続に際して死亡日時如何により遺産の行先が異なる場合があることに鑑みれば、深刻な紛争が容易に想起できる。刑法の「お約束」的事例問題では、臓器提供者を殴打して脳死状態に陥らせた犯人の罪責が殺人未遂や傷害に留まるという結論もあり得る。そのような主張・認定が可能なのか、当事者の意思による選択を認めるのか、詳論の余裕はないが、「臓器移植に関する法律だから」という一言は済まない難問である。
3 脳死論争の意義
最後に、脳死に関する論争点や論争理由を確認しておく。
伝統的な三徴候も脳機能の認識方法であり、その意味では昔から脳死を以て死だと理解されていた。現在の脳死は、三徴候に依ることなく脳機能を認識できるようになったことから提示された概念である。脳死否定説も、脳死が個体死だという医学的判断自体を否定している訳ではない。医学的・生物学的に判断された死をそのまま社会的・法的に受け入れることができるのかという問題提起であり、医学的・生物学的な判断だけでは済まない筈だと論じているのである。
臓器移植法に基づく脳死判定でも、法的に要求される2回の判定のうち、どちらの日時を死亡診断書に記載するべきか、という議論があった。判定を2回要求する趣旨は、万一の誤診を想定した用心である。だから、医学的に判断するなら、1回目判定で脳死は確認済であり、2回目判定を以て「1回目判定は正しかった」と確認されたのだから、真実の死亡日時として1回目判定日時を記載するべきだという結論を導き得る。医学界ではこれが有力説だったらしい。しかし、厚生省は2回目判定日時を死亡日時として記載せよという通知を発した。臓器移植法に基づく死体扱いは2回目判定を以て開始されるのだから、同法に基づく死亡診断は2回目判定だという理解である。
また、臓器移植を予定しない脳死体の場合、医学的に脳死だと確実に判断されても、直ちに死亡診断を行うとは限らない。多くの場合、家族は人工心肺器の作動継続を希望する。間違いなく脳死だ、医学的には既に死体だ、と正しく理解していても、復活の期待があり得ない夢想だと判っていても、死体扱いを承諾するには相当の時間を要するのが通常である。だから、家族が患者の死を受け入れるのを待って人工心肺器の電源を切り、心停止を以て死亡診断を行う。
脳死でなくても、同様の事態はままある。素人でも一見明白に死体だと判る場合は別として、心肺停止状態で救急搬送される場合、救急車内で救命士が蘇生措置を執る。既に死亡していて蘇生不可能だと判断できても、救命士は死亡診断の権限を持たない。病院に搬入されたら、医師が引き継ぐ。救命のために搬入されたのだから、無駄だと判っていても、蘇生措置を継続する。それが通常らしいし、家族の心情に鑑みれば、医学や法律を措いても、それが人の道というものだ。そして、相当時間の蘇生措置の後に、やはり蘇生しないと確認してから、死亡診断を行う。真実は数時間前に自宅で死亡したと判断できても、死亡診断書には診断日時に病院で死亡したと記載される。厚生労働省によれば、死亡診断までは「診療継続中の患者とみなす」措置である。
以上の例は、いずれも、医学的に判断される「真実の死」と異なる死亡診断が行われる場面である。医学的な死が直ちに社会的に受け入れられるとは限らない。医学的な死を以て法を適用すると不合理な結論を導くことがある。典型例として、人工心肺器作動その他の蘇生措置は、死体に対する無意味な行為であって医療行為ではなかったことになる。医学的にはその通りだとしても、医療行為でなければ費用は医療保険の対象にならない。如何なる名目で誰がどれだけ負担するのか、かなり厄介な問題が生じる。
このような事態への対応として、医学的には既に死体になったと判断できても、法律上は生体として扱うことがある。医学的な死と異なる死亡診断が、現に行われているのである。
脳死肯定説によれば、これは真実と異なる擬制だということになる。これに対して、脳死否定説によれば、当該死亡診断は社会的・法的に正しく判断された死であることになる。死をそのように社会的・法的な概念として論じるべきだという主張が、脳死否定説なのである。臓器移植法6条3項には、1項の臓器提供意思とは別に、脳死判定に従う意思に関する規定がある。医学的判断と無関係な当事者の意思を脳死判定の要件としていることも、脳死論争の反映である。
賛否は自由に議論すればよい。いずれにしても、脳死否定説に対して「医学の知見を受け入れない頑迷」という誤ったラベルを貼ってはならない。
(完)
(平30・10・15)