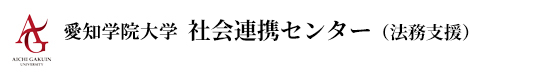コロナと大学-ドイツと日本
愛知学院大学法務支援センター 教授 高橋 洋
今更ですが、新型コロナ感染症は、日本だけでなく、世界の景色を変えました。その影響は飲食店や交通事業者だけでなく、様々な産業に及んでいます。教育界は、といえば、その消費者(学生・生徒・児童)が、容易には学校を離れることができないために、授業料という売り上げにはそれほど大きな影響は、未だ出ていないように見えます。しかし、学生のバイト先が減り、また親の収入が減れば、今後どうなるか、予断を許しません。
ドイツは日本よりも感染者数も死亡者も格段に多く、深刻な国境閉鎖、都市閉鎖(いわゆるロックダウン)を経験しています。大学も長期にわたって閉鎖され、教育も研究もストップしました。そのあたりをフランクフルト大学教授ウーヴェ・フォルクマンは、ある雑誌で次のような述べています。
「先週の週明けに最後に訪れたとき、大学では静寂が支配していた。メンザ(食堂)やカフェは、既に長期にわたって閉鎖されていたが、今や閉鎖は建物全体に及んでいた。図書館にも誰もおらず、いつもであれば、どのドアでも開けることができた研究者身分証も全くダメだった。大学当局と学部当局は、当面の業務の継続に関する通知を送ってきたが、皆極めて限定的な期限付きのものであった。今出されているレポートの〆切りは、最初いったん21日延長され、国家試験はなんとか続行されることになっているが、いつまで続けられるのか、なされた採点が明日にはまた紙くずになってしまうのかどうか、誰にもわからない。夏学期の授業はどうなるのか?さしあたり開講されるのか?場合によっては、オンライン授業に切り替えられるのか、場合にもよるが、そう素早く手はずを整えることはできないから、それもだめか?最終的には、著名なウィルス学者の一人(誰かは忘れてしまったが、人はしばらくすると混乱してしまう)が言うように、仮に全学年が2ゼメスターを失ってしまっても仕方がない、ということであろう。」(Der Staat(国家)、2020年1号巻頭言より) これは昨年の2月から3月頃に書かれたものであろうが、当時の状況が伝わってきます。しかし、その後、一向に感染は収まる気配を見せず、大学の研究者は、自宅の研究室(ホーム・オフィス)に閉じ込められてしまうことになります。教授のこの巻頭言の表題も「ホームオフィス便り」となっています。こうしてドイツでも対面での授業がなくなり、それだけではなく、学会や学内の会議ですら、Zoom(オンラインでの会議用アプリ)を使って行われるようになります。
実はこうした事態が学問にとって危機的なのだ、と述べるのが、ミュンスター大学教授のオリバー・レプジウスです。先ほどと同じ雑誌の半年後の号のやはり巻頭言で、次のように言っています。すなわち、今社会はコロナの感染を防ぐために、その最大の手段として見知らぬ者との偶然の接触を防ぐ(日本的に言えば「三密回避」)ことに躍起となっているが、そのような状況に、学問とその研究機関たる大学が苦んでいる、「というのも、大学は、講義室においてであれ、会議であれ、偶然的接触に頼らざるを得ないからである。大学は、それ自体として、質問、討論、反論、講演、講義の形で個人化された精神が出会う言説の場であり、人的な社団である。人間と、それらの合目的的な接触なしには、学問は、そして大学は成り立たない。目下のところ、事態はまさに以下のようである。すなわち、大学当局は、―建物管理権、大学法、そして対感染症保護法からなる見通しのきかない法に支えられつつ―その建物を閉鎖し、そして明らかに他の公共建築物よりもためらいがちに、最小限ではあるが、再び通行できるようにした。なお相変わらず、厳しい制限が講義室にはかかっている。学問的会合は、全体として特に拒否され、最善でも1年間延期された。一定の距離を取るのが可能で、しかも支払の可能な空間は、もはやどこにもない。大学当局は、大教室の使用を拒否している。各アカデミーは、閉鎖に全く賛成であることを宣言している。」レプジウス教授は、「Covid-19は世界的蔓延下で定着して行くであろう、―何か他のことが起こりうるであろうか?―。それはあちこちで減退し、あちこちで爆発するであろう。それとは、継続的に闘っていかねばならないであろう。(中略)コロナと共に生きることを、我々は学ばなければならない。」という見解を持っています。もちろん憲法学者ですから、医学的に正しいかは別ですが(もっとも医学者がこの点で正しくないことを言っている(いた)ことも、我々はよく目にしますが)、一応の見識であろうかと思います。ワクチン接種が始まって一定の見通しが出てきましたが、慎重に、偶然的接触が不可避な人たちの場を回復していきたいものです。
(AGULS第47号(2021/6/25)掲載 )
今更ですが、新型コロナ感染症は、日本だけでなく、世界の景色を変えました。その影響は飲食店や交通事業者だけでなく、様々な産業に及んでいます。教育界は、といえば、その消費者(学生・生徒・児童)が、容易には学校を離れることができないために、授業料という売り上げにはそれほど大きな影響は、未だ出ていないように見えます。しかし、学生のバイト先が減り、また親の収入が減れば、今後どうなるか、予断を許しません。
ドイツは日本よりも感染者数も死亡者も格段に多く、深刻な国境閉鎖、都市閉鎖(いわゆるロックダウン)を経験しています。大学も長期にわたって閉鎖され、教育も研究もストップしました。そのあたりをフランクフルト大学教授ウーヴェ・フォルクマンは、ある雑誌で次のような述べています。
「先週の週明けに最後に訪れたとき、大学では静寂が支配していた。メンザ(食堂)やカフェは、既に長期にわたって閉鎖されていたが、今や閉鎖は建物全体に及んでいた。図書館にも誰もおらず、いつもであれば、どのドアでも開けることができた研究者身分証も全くダメだった。大学当局と学部当局は、当面の業務の継続に関する通知を送ってきたが、皆極めて限定的な期限付きのものであった。今出されているレポートの〆切りは、最初いったん21日延長され、国家試験はなんとか続行されることになっているが、いつまで続けられるのか、なされた採点が明日にはまた紙くずになってしまうのかどうか、誰にもわからない。夏学期の授業はどうなるのか?さしあたり開講されるのか?場合によっては、オンライン授業に切り替えられるのか、場合にもよるが、そう素早く手はずを整えることはできないから、それもだめか?最終的には、著名なウィルス学者の一人(誰かは忘れてしまったが、人はしばらくすると混乱してしまう)が言うように、仮に全学年が2ゼメスターを失ってしまっても仕方がない、ということであろう。」(Der Staat(国家)、2020年1号巻頭言より) これは昨年の2月から3月頃に書かれたものであろうが、当時の状況が伝わってきます。しかし、その後、一向に感染は収まる気配を見せず、大学の研究者は、自宅の研究室(ホーム・オフィス)に閉じ込められてしまうことになります。教授のこの巻頭言の表題も「ホームオフィス便り」となっています。こうしてドイツでも対面での授業がなくなり、それだけではなく、学会や学内の会議ですら、Zoom(オンラインでの会議用アプリ)を使って行われるようになります。
実はこうした事態が学問にとって危機的なのだ、と述べるのが、ミュンスター大学教授のオリバー・レプジウスです。先ほどと同じ雑誌の半年後の号のやはり巻頭言で、次のように言っています。すなわち、今社会はコロナの感染を防ぐために、その最大の手段として見知らぬ者との偶然の接触を防ぐ(日本的に言えば「三密回避」)ことに躍起となっているが、そのような状況に、学問とその研究機関たる大学が苦んでいる、「というのも、大学は、講義室においてであれ、会議であれ、偶然的接触に頼らざるを得ないからである。大学は、それ自体として、質問、討論、反論、講演、講義の形で個人化された精神が出会う言説の場であり、人的な社団である。人間と、それらの合目的的な接触なしには、学問は、そして大学は成り立たない。目下のところ、事態はまさに以下のようである。すなわち、大学当局は、―建物管理権、大学法、そして対感染症保護法からなる見通しのきかない法に支えられつつ―その建物を閉鎖し、そして明らかに他の公共建築物よりもためらいがちに、最小限ではあるが、再び通行できるようにした。なお相変わらず、厳しい制限が講義室にはかかっている。学問的会合は、全体として特に拒否され、最善でも1年間延期された。一定の距離を取るのが可能で、しかも支払の可能な空間は、もはやどこにもない。大学当局は、大教室の使用を拒否している。各アカデミーは、閉鎖に全く賛成であることを宣言している。」レプジウス教授は、「Covid-19は世界的蔓延下で定着して行くであろう、―何か他のことが起こりうるであろうか?―。それはあちこちで減退し、あちこちで爆発するであろう。それとは、継続的に闘っていかねばならないであろう。(中略)コロナと共に生きることを、我々は学ばなければならない。」という見解を持っています。もちろん憲法学者ですから、医学的に正しいかは別ですが(もっとも医学者がこの点で正しくないことを言っている(いた)ことも、我々はよく目にしますが)、一応の見識であろうかと思います。ワクチン接種が始まって一定の見通しが出てきましたが、慎重に、偶然的接触が不可避な人たちの場を回復していきたいものです。
(AGULS第47号(2021/6/25)掲載 )