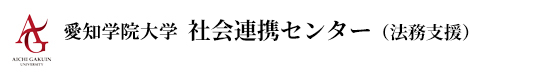法と裁判について(第4=最終回)
愛知学院大学法務支援センター教授 梅田 豊
前回は現代の刑事裁判の基本的な考え方を理解するための比較対象として「遠山の金さん」の「裁き」の問題点を指摘しました。
現代の裁判においては、裁判官は、予断偏見を持たずにあくまでも法廷に出された証拠を中立・公平な第三者の立場で客観的に評価・判断しなければなりません。もし裁判官がその事件を目撃していたとすれば、当然予断を持つことになるでしょう。判断の中立・公平・客観性を担保するためには、そのような予断を持たない他の裁判官に交代させるべきだと考えられるわけです。
他方で被告人には、自分が有罪とされるかもしれない証言に対して反対尋問をする権利が保障されています(憲法上は証人審問権と呼ばれます。憲法37条2項)。例えば、下町での金さんは結構遊び人でお酒を飲んで酔っぱらっていることも多かったとします。そこで、被告人の弁護人が金さんに対して反対尋問すると当日もお酒を飲んでいたことが判明しました。弁護人が、「実際は酔っぱらって寝込んでしまい、夢でも見ていただけではないか」と追及すると、金さんはしどろもどろになってしまいました。果たして金さんの「被告人(悪人たち)の悪事を目撃した」という証言は本当に信用できるのでしょうか。そういうこともあり得るわけです。
万が一にも不確かな証拠で被告人を有罪としてしまうとすれば大変なことですね。人間が同じ人間を裁く際には、思い込みや予断・偏見からいわゆる誤判・冤罪を引き起こしてしまうことがあり得ます。現代の法制度・裁判制度は、できる限りそれを避けるために様々な工夫を積み重ねてきた人類の歴史の上に構築されています。黙秘権、令状主義(身体拘束や捜索・差押えには裁判官の令状が必要)、弁護人依頼権や先ほどの反対尋問権などの様々な権利保障のシステム(包括的には適正手続の保障と呼ばれます。憲法31条)は、万が一にも誤判・冤罪を引き起こすことのないようにするための人類の歴史的知恵なのです。
有罪判決が下されるまでは被告人は「無罪の推定」を受けるという原則や検察官は合理的な疑問を残さない程度まで被告人の有罪を証明しなければならないという原則など、被告人の利益に配慮した様々な原則もあります。その結果、実は本当の犯人である者が無罪になってしまうということもあるかもしれません。しかし「10人の真犯人を逃すとも、1人の無辜(無実の人)を罰するなかれ」という法格言があります。もし「1人くらい犠牲になっても良いじゃないか」と考えてしまうとすれば、結局犠牲者は1人では済まないことになってしまうでしょう。
さて、この連載では犯罪者(その人が犯罪を犯したこと)をどのようにして判断するかという刑事手続・刑事裁判(刑事訴訟法の対象となる分野)の側面からの話が中心となりました(紙幅の制約もあり十分ではありませんが)。その前提となるそもそも犯罪とは何かという問題(刑法の対象となる分野)については踏み込んだお話はできませんでした。それ以外にもお話すべきことはまだ沢山ありますが、一旦この辺で一区切りをつけたいと思います。
(AGULS第7号(2018/02/25)掲載)
前回は現代の刑事裁判の基本的な考え方を理解するための比較対象として「遠山の金さん」の「裁き」の問題点を指摘しました。
現代の裁判においては、裁判官は、予断偏見を持たずにあくまでも法廷に出された証拠を中立・公平な第三者の立場で客観的に評価・判断しなければなりません。もし裁判官がその事件を目撃していたとすれば、当然予断を持つことになるでしょう。判断の中立・公平・客観性を担保するためには、そのような予断を持たない他の裁判官に交代させるべきだと考えられるわけです。
他方で被告人には、自分が有罪とされるかもしれない証言に対して反対尋問をする権利が保障されています(憲法上は証人審問権と呼ばれます。憲法37条2項)。例えば、下町での金さんは結構遊び人でお酒を飲んで酔っぱらっていることも多かったとします。そこで、被告人の弁護人が金さんに対して反対尋問すると当日もお酒を飲んでいたことが判明しました。弁護人が、「実際は酔っぱらって寝込んでしまい、夢でも見ていただけではないか」と追及すると、金さんはしどろもどろになってしまいました。果たして金さんの「被告人(悪人たち)の悪事を目撃した」という証言は本当に信用できるのでしょうか。そういうこともあり得るわけです。
万が一にも不確かな証拠で被告人を有罪としてしまうとすれば大変なことですね。人間が同じ人間を裁く際には、思い込みや予断・偏見からいわゆる誤判・冤罪を引き起こしてしまうことがあり得ます。現代の法制度・裁判制度は、できる限りそれを避けるために様々な工夫を積み重ねてきた人類の歴史の上に構築されています。黙秘権、令状主義(身体拘束や捜索・差押えには裁判官の令状が必要)、弁護人依頼権や先ほどの反対尋問権などの様々な権利保障のシステム(包括的には適正手続の保障と呼ばれます。憲法31条)は、万が一にも誤判・冤罪を引き起こすことのないようにするための人類の歴史的知恵なのです。
有罪判決が下されるまでは被告人は「無罪の推定」を受けるという原則や検察官は合理的な疑問を残さない程度まで被告人の有罪を証明しなければならないという原則など、被告人の利益に配慮した様々な原則もあります。その結果、実は本当の犯人である者が無罪になってしまうということもあるかもしれません。しかし「10人の真犯人を逃すとも、1人の無辜(無実の人)を罰するなかれ」という法格言があります。もし「1人くらい犠牲になっても良いじゃないか」と考えてしまうとすれば、結局犠牲者は1人では済まないことになってしまうでしょう。
さて、この連載では犯罪者(その人が犯罪を犯したこと)をどのようにして判断するかという刑事手続・刑事裁判(刑事訴訟法の対象となる分野)の側面からの話が中心となりました(紙幅の制約もあり十分ではありませんが)。その前提となるそもそも犯罪とは何かという問題(刑法の対象となる分野)については踏み込んだお話はできませんでした。それ以外にもお話すべきことはまだ沢山ありますが、一旦この辺で一区切りをつけたいと思います。
(AGULS第7号(2018/02/25)掲載)