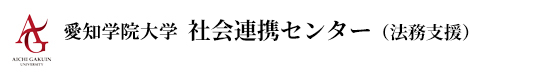日本の検察官と捜査の課題(1)
愛知学院大学教養部教授 梅田 豊
新型コロナウイルスにより社会全体が揺れ動いている中で、東京高検検事長の定年延長とそれに引き続く検察庁法改正案の提出が大きな話題になりました。法案に先立って閣議決定された黒川弘務前東京高検検事長の定年延長(政府は国家公務員法を根拠としました)は、その法的根拠に疑問があります。1981年の政府答弁も明言しているように、国家公務員法の定年規定は「検察官に適用しない」と長年解釈されてきたからです。にもかかわらす、この定年延長を後付けするような検察庁法改正案が国家公務員法改正案とセットで提出されたため、国会でも野党が批判し、自民党内でも疑問の声が出されました。ネット上でも、「#検察庁改正法案に抗議します」というツイートが一気に数百万にまで拡散し、さらに元検事総長ら検察OBも異例の抗議文を出すなど、抗議の波が大きく広がりました。
ところが、週刊文春の「賭けマージャン報道」(緊急事態宣言発令中に2回、黒川氏と産経新聞記者2人、朝日新聞元記者の計4人が賭けマージャンに興じていた)で事態は急転します。安倍首相は世論の反発などを踏まえ、5月17日法案見送りを菅官房長官に指示しました。結局、この「賭けマージャン報道」で黒川氏は辞職に追い込まれました(その後の黒川氏に対する処分が「訓告」という非常に軽いものであったことも問題になりましたが)。その後、検察庁法改正案も廃案になり、ひとまず問題は一段落したようです。
ところで、日本の検察官は世界でもまれに見る強大な権限を持つ機関です。通常の刑事事件では、第一次的な捜査機関である警察が捜査し、証拠が揃うと検察官に事件が送致されます(いわゆる「送検」)。検察官は、必要な場合は自ら補充捜査を行い又は警察にそれを指示して、公判に耐えられる十分な証拠の有無をチェックした上で、事件を起訴します。その点で、通常の事件に関しては、検察官は第二次的な捜査機関と位置付けられます。
それに対して、特捜部は、東京・大阪・名古屋の地方検察庁に置かれている部で、公正取引委員会などが法令に基づき告発をした事件について捜査する他、汚職・企業犯罪等について独自捜査を行います。更に、検察官は、事件の起訴・不起訴について、決定的な権限を持っています。その上、公判では、被告人を有罪とするために、証拠を提出する権限と義務を負っています。
このように捜査の権限、起訴の権限、公判での訴追側当事者としての権限と、刑事手続のほぼ全ての段階で非常に大きな権限を与えられているのです。それに加えて、日本の刑事裁判は「有罪率99.9%」と言われるように、検察官が起訴すれば、まず間違いなく有罪というのが現実です。そこには、様々な問題が潜んでいるのです(それについては次回述べます)が、いずれにしても検察官の権限を政府が人事権を通して自由にコントロールできるとすれば、それは非常に危険な事態だと言わなければなりません。今回の東京高検検事長の定年延長問題は、そのことを思い起こさせる出来事であったように思われます。
次回は、日本の捜査に関わる諸問題について検討します。
(AGULS第36号(2020/7/25)掲載 )
新型コロナウイルスにより社会全体が揺れ動いている中で、東京高検検事長の定年延長とそれに引き続く検察庁法改正案の提出が大きな話題になりました。法案に先立って閣議決定された黒川弘務前東京高検検事長の定年延長(政府は国家公務員法を根拠としました)は、その法的根拠に疑問があります。1981年の政府答弁も明言しているように、国家公務員法の定年規定は「検察官に適用しない」と長年解釈されてきたからです。にもかかわらす、この定年延長を後付けするような検察庁法改正案が国家公務員法改正案とセットで提出されたため、国会でも野党が批判し、自民党内でも疑問の声が出されました。ネット上でも、「#検察庁改正法案に抗議します」というツイートが一気に数百万にまで拡散し、さらに元検事総長ら検察OBも異例の抗議文を出すなど、抗議の波が大きく広がりました。
ところが、週刊文春の「賭けマージャン報道」(緊急事態宣言発令中に2回、黒川氏と産経新聞記者2人、朝日新聞元記者の計4人が賭けマージャンに興じていた)で事態は急転します。安倍首相は世論の反発などを踏まえ、5月17日法案見送りを菅官房長官に指示しました。結局、この「賭けマージャン報道」で黒川氏は辞職に追い込まれました(その後の黒川氏に対する処分が「訓告」という非常に軽いものであったことも問題になりましたが)。その後、検察庁法改正案も廃案になり、ひとまず問題は一段落したようです。
ところで、日本の検察官は世界でもまれに見る強大な権限を持つ機関です。通常の刑事事件では、第一次的な捜査機関である警察が捜査し、証拠が揃うと検察官に事件が送致されます(いわゆる「送検」)。検察官は、必要な場合は自ら補充捜査を行い又は警察にそれを指示して、公判に耐えられる十分な証拠の有無をチェックした上で、事件を起訴します。その点で、通常の事件に関しては、検察官は第二次的な捜査機関と位置付けられます。
それに対して、特捜部は、東京・大阪・名古屋の地方検察庁に置かれている部で、公正取引委員会などが法令に基づき告発をした事件について捜査する他、汚職・企業犯罪等について独自捜査を行います。更に、検察官は、事件の起訴・不起訴について、決定的な権限を持っています。その上、公判では、被告人を有罪とするために、証拠を提出する権限と義務を負っています。
このように捜査の権限、起訴の権限、公判での訴追側当事者としての権限と、刑事手続のほぼ全ての段階で非常に大きな権限を与えられているのです。それに加えて、日本の刑事裁判は「有罪率99.9%」と言われるように、検察官が起訴すれば、まず間違いなく有罪というのが現実です。そこには、様々な問題が潜んでいるのです(それについては次回述べます)が、いずれにしても検察官の権限を政府が人事権を通して自由にコントロールできるとすれば、それは非常に危険な事態だと言わなければなりません。今回の東京高検検事長の定年延長問題は、そのことを思い起こさせる出来事であったように思われます。
次回は、日本の捜査に関わる諸問題について検討します。
(AGULS第36号(2020/7/25)掲載 )