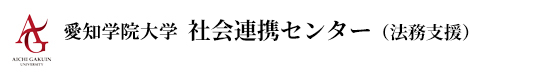日本の検察官と捜査の課題(2)
愛知学院大学教養部教授 梅田 豊
日本の捜査(特に検察捜査)の問題点について、世界的な注目を集めたのが、日産自動車のカルロス・ゴーン元会長を巡る一連の捜査でした。このゴーン事件は、勾留保釈中に被告人が国外逃亡するという驚くべき事態に進展しましたが、もちろん保釈中の国外逃亡が違法であることは言うまでもありません。ただ、ここではその問題をひとまず置き、その間のゴーン被告人に対する捜査(身柄の扱い・取調べ等)のあり方に対する国際社会の批判について考えてみます。
ゴーン事件の捜査に関わり日本の刑事司法が海外から特に批判された点は、被告人(被疑者)の取調べに際して弁護人の立会いが認められていないことと、取調べと勾留の運用が連動していることでした。「共産主義の中国の出来事か? いや、資本主義の日本だ」(米紙)、「弁護人の立会いなしでの取り調べが毎日続く」(仏紙)など、海外メディアは日本の刑事司法を「人権無視」として痛烈に批判しました。
米国では、すでに1966年のミランダ判決により、捜査官は身体拘束中の取調べに先立ち、「黙秘権」や「弁護人の立会いを求める権利」などを被疑者に告げなければならないという原則が採用され、これは確立したルールとなっています。その後、ヨーロッパ諸国でも、弁護人立会いを原則とするようになってきました。現在では、日米英仏独伊韓の7カ国の中で、取調べへの弁護人立会いを認めていないのは、日本だけなのです。弁護人立会いは今では世界の潮流ともいえ、ゴーン事件捜査における取扱いは、家族などとの接見も禁じられる状況も含め、海外メディアには「人権無視」と映るわけです。
問題は勾留の運用にもあります。ゴーン被告人の勾留は、保釈が認められまでに最終的に108日に及びました。検察官は、保釈に反対していましたので、さらに長期の身体拘束で自白を迫るつもりだったのでしょう。しかし、そのような捜査手法に対しても批判があります。日本では起訴後、弁護側が保釈を求めても、検察側が「証拠隠滅の恐れ」などを理由に反対し、裁判所が保釈を認めないケースが多いのです。司法統計によると、2017年に起訴から判決までに保釈された割合は約3割にとどまり、特に否認すれば起訴後も、勾留が長引く傾向にあります。他方で、自白をすると保釈が認められることが多く、このような運用は、自白を取るために勾留を利用するやり方として「人質司法」という言葉が 定着しています。このようなやり方は、欧米からは「推定無罪」の原則を侵すものと見られています。
日本の法務省・検察側は「他国の制度が自国と違うからといって簡単に批判するのはいかがなものか」と反論します。しかし、今回の事件は、欧州の大企業のトップが日本へのビジネス出張に二の足を踏ませるような影響をみせている、とも言われます。フランスなどでは、「これまで 非常に良好だった日本のイメージをひどく傷つけている」とし、これまで好印象だった日本ブランドを傷つけかねないとも指摘されています。
その点で、むしろグローバルスタンダードに合った刑事司法へ転換するきっかけとすべきではないかと思われます。
(AGULS第37号(2020/8/25)掲載 )
日本の捜査(特に検察捜査)の問題点について、世界的な注目を集めたのが、日産自動車のカルロス・ゴーン元会長を巡る一連の捜査でした。このゴーン事件は、勾留保釈中に被告人が国外逃亡するという驚くべき事態に進展しましたが、もちろん保釈中の国外逃亡が違法であることは言うまでもありません。ただ、ここではその問題をひとまず置き、その間のゴーン被告人に対する捜査(身柄の扱い・取調べ等)のあり方に対する国際社会の批判について考えてみます。
ゴーン事件の捜査に関わり日本の刑事司法が海外から特に批判された点は、被告人(被疑者)の取調べに際して弁護人の立会いが認められていないことと、取調べと勾留の運用が連動していることでした。「共産主義の中国の出来事か? いや、資本主義の日本だ」(米紙)、「弁護人の立会いなしでの取り調べが毎日続く」(仏紙)など、海外メディアは日本の刑事司法を「人権無視」として痛烈に批判しました。
米国では、すでに1966年のミランダ判決により、捜査官は身体拘束中の取調べに先立ち、「黙秘権」や「弁護人の立会いを求める権利」などを被疑者に告げなければならないという原則が採用され、これは確立したルールとなっています。その後、ヨーロッパ諸国でも、弁護人立会いを原則とするようになってきました。現在では、日米英仏独伊韓の7カ国の中で、取調べへの弁護人立会いを認めていないのは、日本だけなのです。弁護人立会いは今では世界の潮流ともいえ、ゴーン事件捜査における取扱いは、家族などとの接見も禁じられる状況も含め、海外メディアには「人権無視」と映るわけです。
問題は勾留の運用にもあります。ゴーン被告人の勾留は、保釈が認められまでに最終的に108日に及びました。検察官は、保釈に反対していましたので、さらに長期の身体拘束で自白を迫るつもりだったのでしょう。しかし、そのような捜査手法に対しても批判があります。日本では起訴後、弁護側が保釈を求めても、検察側が「証拠隠滅の恐れ」などを理由に反対し、裁判所が保釈を認めないケースが多いのです。司法統計によると、2017年に起訴から判決までに保釈された割合は約3割にとどまり、特に否認すれば起訴後も、勾留が長引く傾向にあります。他方で、自白をすると保釈が認められることが多く、このような運用は、自白を取るために勾留を利用するやり方として「人質司法」という言葉が 定着しています。このようなやり方は、欧米からは「推定無罪」の原則を侵すものと見られています。
日本の法務省・検察側は「他国の制度が自国と違うからといって簡単に批判するのはいかがなものか」と反論します。しかし、今回の事件は、欧州の大企業のトップが日本へのビジネス出張に二の足を踏ませるような影響をみせている、とも言われます。フランスなどでは、「これまで 非常に良好だった日本のイメージをひどく傷つけている」とし、これまで好印象だった日本ブランドを傷つけかねないとも指摘されています。
その点で、むしろグローバルスタンダードに合った刑事司法へ転換するきっかけとすべきではないかと思われます。
(AGULS第37号(2020/8/25)掲載 )