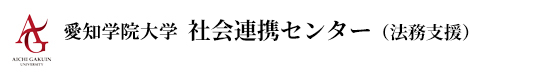「お墓と法律(その1)」
社会連携センター(法務支援) 田中 淳子
民法上の権利の行使や義務の履行ができる権利の主体になれるのは、いつからか。権利の主体の「始期」について、民法第3条は「私権の享有は、出生に始まる」と規定しています。例外として、まだ出生していない胎児であっても、例えば、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」(民法886条1項)とし、権利の主体になることを認めています。しかし、同条2項では、「前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない」としていますので、死産の場合には相続権はないことになります。権利の主体の基本は、生きている」ことになります。では、権利の「終期」はいつか。なんとなく、前述のしくみからもわかるように「死亡時」ということになりそうです。しかし、実のところ、民法には、始期のような「〇〇の時に終わる」という明確な規定は存在していないのです。死亡すれば、契約の締結の意思表示や、賃貸借契約の解除の意思表示等、契約の基礎となる要件を満たすことができないし、義務の履行もできません。死亡によって相続が開始すれば、被相続人の生前の権利・義務は包括的に相続人が承継取得する仕組みとなっていますので、「死亡時」が権利の主体の終期となると考えられます。
では、主体でなくなるとすると、その後の遺体や遺骨は、どうなるのか。民法では、主体でなければ、権利の客体、すなわち、「物」となります。民法第85条には「この法律において『物』とは、有体物をいう」と規定しています。その「物」には、「不動産」と「動産」(不動産以外の物は、すべて動産とする)がある(同法第86条)と規定されています。したがって、遺体、遺骨はさっきまで「主体」であったのに死亡の瞬間から「客体」=「物」となるのか。この点についても民法は明確な規定をおいていません。亡くなった方の遺体や遺骨(焼骨)、遺灰等については、人体の一部に関する特別法(臓器移植法等)のような利用等に関する特別の規定があるわけでもありません。たしかに、墓地埋葬法があります。しかし、これは、公衆衛生上の観点(同法1条)により、遺体を放置したままにしないための規定といえます。墓地への埋葬、火葬に関する規定のため、「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいい、「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可をうけた区域をいい、「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう(同法2条)と埋葬についての定義が規定されています。しかし、「埋葬」、「埋蔵」、「収蔵」された遺体、遺骨の法的性質を明らかにするものではありません。
今日、火葬が99,7%を超えており、一般的となっています。土葬の時代と比べ、人々は、近しい方の焼骨や遺骨を目にすることが多くなり、遺骨や墓地等をめぐる紛争が増加しています他方、最近は、完全に遺骨が焼却され遺灰のみが残る施設もあり、家族に迷惑をかけたくないとして散骨、散灰等によって、墓地等、埋葬場所もいらないとする人も増えています。祖先が眠る「○○家」の墓が無縁化した場合の遺骨等の管理、撤去の問題や引き取り手が見つからないことで自治体の事務、財政の負担も急増しています。
遺骨やお墓等は、弔いの対象でとして「祭祀」を行うために用いられてきました。民法もそのような場面を想定して規定されています。しかし、親族関係の希薄化等、弔いそれ自体に関心が薄れた中で誰が祭祀を行うか等、民法が想定していない問題に対しどのように対応すればよいのか。具体的な法的問題については、次回に。
民法上の権利の行使や義務の履行ができる権利の主体になれるのは、いつからか。権利の主体の「始期」について、民法第3条は「私権の享有は、出生に始まる」と規定しています。例外として、まだ出生していない胎児であっても、例えば、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」(民法886条1項)とし、権利の主体になることを認めています。しかし、同条2項では、「前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない」としていますので、死産の場合には相続権はないことになります。権利の主体の基本は、生きている」ことになります。では、権利の「終期」はいつか。なんとなく、前述のしくみからもわかるように「死亡時」ということになりそうです。しかし、実のところ、民法には、始期のような「〇〇の時に終わる」という明確な規定は存在していないのです。死亡すれば、契約の締結の意思表示や、賃貸借契約の解除の意思表示等、契約の基礎となる要件を満たすことができないし、義務の履行もできません。死亡によって相続が開始すれば、被相続人の生前の権利・義務は包括的に相続人が承継取得する仕組みとなっていますので、「死亡時」が権利の主体の終期となると考えられます。
では、主体でなくなるとすると、その後の遺体や遺骨は、どうなるのか。民法では、主体でなければ、権利の客体、すなわち、「物」となります。民法第85条には「この法律において『物』とは、有体物をいう」と規定しています。その「物」には、「不動産」と「動産」(不動産以外の物は、すべて動産とする)がある(同法第86条)と規定されています。したがって、遺体、遺骨はさっきまで「主体」であったのに死亡の瞬間から「客体」=「物」となるのか。この点についても民法は明確な規定をおいていません。亡くなった方の遺体や遺骨(焼骨)、遺灰等については、人体の一部に関する特別法(臓器移植法等)のような利用等に関する特別の規定があるわけでもありません。たしかに、墓地埋葬法があります。しかし、これは、公衆衛生上の観点(同法1条)により、遺体を放置したままにしないための規定といえます。墓地への埋葬、火葬に関する規定のため、「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいい、「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可をうけた区域をいい、「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう(同法2条)と埋葬についての定義が規定されています。しかし、「埋葬」、「埋蔵」、「収蔵」された遺体、遺骨の法的性質を明らかにするものではありません。
今日、火葬が99,7%を超えており、一般的となっています。土葬の時代と比べ、人々は、近しい方の焼骨や遺骨を目にすることが多くなり、遺骨や墓地等をめぐる紛争が増加しています他方、最近は、完全に遺骨が焼却され遺灰のみが残る施設もあり、家族に迷惑をかけたくないとして散骨、散灰等によって、墓地等、埋葬場所もいらないとする人も増えています。祖先が眠る「○○家」の墓が無縁化した場合の遺骨等の管理、撤去の問題や引き取り手が見つからないことで自治体の事務、財政の負担も急増しています。
遺骨やお墓等は、弔いの対象でとして「祭祀」を行うために用いられてきました。民法もそのような場面を想定して規定されています。しかし、親族関係の希薄化等、弔いそれ自体に関心が薄れた中で誰が祭祀を行うか等、民法が想定していない問題に対しどのように対応すればよいのか。具体的な法的問題については、次回に。