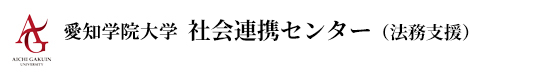自然災害による被災者の債務整理について
愛知学院大学特別教授・弁護士 國田武二郎
Q:今般の能登半島地震で家が倒壊するなどの被害を受けました。生活再建の目途も立っていません。金融機関に月末に支払わねばならぬ住宅ローンの支払もあるのですが、自分たちの生活をどうするかを考えることで精一杯で、ローンの返済まで余裕がありません。
A:まずは、被災に遭った方々に心からお見舞い申し上げます。能登半島に未曽有の被害をもたらした大地震の影響によって、住宅ローン等を借りている個人や事業性ローン等を借りている個人事業主が、債務を抱えたままでは生活の再スターもできません。それでは、債務者(=被災者)が災害から復興のために立ち上がることは経済的にも精神的にも困難であり極めて重大な問題です。そこで、東日本大震災やその後に発生した地震、大規模な風水害などの自然災害を受けた人達(債務者)の復興のために「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」というものがあります。
このガイドラインは、自然災害によって、住宅ローン、住宅リフォームや事業性ローン等の既往債務の弁済ができなくなった個人債務者については、法的倒産手続きによらず、債権者(銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合、政府系金融機関、貸金業者、リース会社、クレジット会社及び債権回収会社並びに信用保証協会、農協信用基金協会等主として金融債務に係る債権者)と債務者の合意に基づき、債務の全部又は一部を減免すること等を内容とする債務整理を公正かつ迅速に行うことを目的としています。債務者(被災者)の債務整理を円滑に進めることが、債務者(被災者)の自助努力による生活や事業の再建を支援し、被災地の復興・再活性化につながるということです。
そこで、取りあえず最も多額のローンを借りている金融機関等に、ガイドラインの手続きを希望することを申出て下さい。対象となる債務者は、住居、勤務先等の生活基盤や事業所、事業設備、取引先等の事業基盤などが災害の影響を受けたことによって、住宅ローン、住宅のリフォームローンや事業性ローンその他の現在の債務を弁済することができないこと又は近い将来において債務を弁済できないことが確実に見込まれる方々です。
手続ですが、まず、①金融機関の受付窓口に行き、「ガイドラインに基づいて、住宅ローンや事業用ローンなどの免除・減額をお願いしたいのですが」と申出て下さい。②申出に対し金融機関等は、年収や資産状況などを尋ねたりしますが、ガイドラインに沿って債務整理を行なうことに同意をした場合、③地元弁護士会や税理士会などに、「登録支援専門家」による手続支援を依頼して下さい。この専門家による支援手続きは無料で受けられます。そして、④専門家の支援を受けながら金融機関等に債務整理をするための申出書や財産目録等の必要書類を金融機関に提出します。⑤提出されれば債務整理が開始され、債務の返済や督促は一時停止されます。⑥さらに、専門家の支援を受けながら、全ての借入先の金融機関と協議して、債務整理の内容を盛り込んだ書類、「調停条項案」を作成し、作成が完成したら、金融機関に提出します。⑦提出を受けた金融融機関は、概ね1か月以内を目安に同意するかどうか検討し、同意が得られた場合、債務者自らが簡易裁判所に赴いて「特定調停」の申立てを行ないます。特定調停とは、債権者と債務者とが裁判所の関与の下で話し合う手続きのことです。費用は1社につき500円程度です(因みに、弁護士に任意整理を依頼すると1社につき2万~5万円程度かかります)⑧そして、特定調停手続きにより調停条項が確定すれば調停調書が作成され「債務整理」が成立します。裁判所も被災したという気の毒な事情も考慮して、債務者(被災者)に有利な内容で調停の内容を決める場合もあるので「特定調停」を利用する価値はあると思います。また、このガイドラインにそって債務整理を進めた場合、①義援金等に加え財産の一部を手元に残せる。②債務整理したことが個人信用情報として登録されないため、新たな借入れに影響が及ばない等というメリットもあります。
但し、特定調書が作成されると、債務者が履行しなかった場合、直ちに強制執行が可能になるので注意して下さい。その他、詳細は、金融機関や専門家にお尋ねください。
(AGULS89号(2024/12/25)掲載)
Q:今般の能登半島地震で家が倒壊するなどの被害を受けました。生活再建の目途も立っていません。金融機関に月末に支払わねばならぬ住宅ローンの支払もあるのですが、自分たちの生活をどうするかを考えることで精一杯で、ローンの返済まで余裕がありません。
A:まずは、被災に遭った方々に心からお見舞い申し上げます。能登半島に未曽有の被害をもたらした大地震の影響によって、住宅ローン等を借りている個人や事業性ローン等を借りている個人事業主が、債務を抱えたままでは生活の再スターもできません。それでは、債務者(=被災者)が災害から復興のために立ち上がることは経済的にも精神的にも困難であり極めて重大な問題です。そこで、東日本大震災やその後に発生した地震、大規模な風水害などの自然災害を受けた人達(債務者)の復興のために「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」というものがあります。
このガイドラインは、自然災害によって、住宅ローン、住宅リフォームや事業性ローン等の既往債務の弁済ができなくなった個人債務者については、法的倒産手続きによらず、債権者(銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合、政府系金融機関、貸金業者、リース会社、クレジット会社及び債権回収会社並びに信用保証協会、農協信用基金協会等主として金融債務に係る債権者)と債務者の合意に基づき、債務の全部又は一部を減免すること等を内容とする債務整理を公正かつ迅速に行うことを目的としています。債務者(被災者)の債務整理を円滑に進めることが、債務者(被災者)の自助努力による生活や事業の再建を支援し、被災地の復興・再活性化につながるということです。
そこで、取りあえず最も多額のローンを借りている金融機関等に、ガイドラインの手続きを希望することを申出て下さい。対象となる債務者は、住居、勤務先等の生活基盤や事業所、事業設備、取引先等の事業基盤などが災害の影響を受けたことによって、住宅ローン、住宅のリフォームローンや事業性ローンその他の現在の債務を弁済することができないこと又は近い将来において債務を弁済できないことが確実に見込まれる方々です。
手続ですが、まず、①金融機関の受付窓口に行き、「ガイドラインに基づいて、住宅ローンや事業用ローンなどの免除・減額をお願いしたいのですが」と申出て下さい。②申出に対し金融機関等は、年収や資産状況などを尋ねたりしますが、ガイドラインに沿って債務整理を行なうことに同意をした場合、③地元弁護士会や税理士会などに、「登録支援専門家」による手続支援を依頼して下さい。この専門家による支援手続きは無料で受けられます。そして、④専門家の支援を受けながら金融機関等に債務整理をするための申出書や財産目録等の必要書類を金融機関に提出します。⑤提出されれば債務整理が開始され、債務の返済や督促は一時停止されます。⑥さらに、専門家の支援を受けながら、全ての借入先の金融機関と協議して、債務整理の内容を盛り込んだ書類、「調停条項案」を作成し、作成が完成したら、金融機関に提出します。⑦提出を受けた金融融機関は、概ね1か月以内を目安に同意するかどうか検討し、同意が得られた場合、債務者自らが簡易裁判所に赴いて「特定調停」の申立てを行ないます。特定調停とは、債権者と債務者とが裁判所の関与の下で話し合う手続きのことです。費用は1社につき500円程度です(因みに、弁護士に任意整理を依頼すると1社につき2万~5万円程度かかります)⑧そして、特定調停手続きにより調停条項が確定すれば調停調書が作成され「債務整理」が成立します。裁判所も被災したという気の毒な事情も考慮して、債務者(被災者)に有利な内容で調停の内容を決める場合もあるので「特定調停」を利用する価値はあると思います。また、このガイドラインにそって債務整理を進めた場合、①義援金等に加え財産の一部を手元に残せる。②債務整理したことが個人信用情報として登録されないため、新たな借入れに影響が及ばない等というメリットもあります。
但し、特定調書が作成されると、債務者が履行しなかった場合、直ちに強制執行が可能になるので注意して下さい。その他、詳細は、金融機関や専門家にお尋ねください。
(AGULS89号(2024/12/25)掲載)