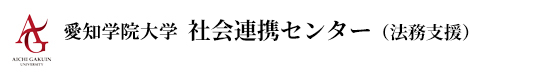ライト・アップの闇
愛知学院大学名誉教授・弁護士 原田保
平成初期の話である。当時まだ愛知学院大学法学部教授であった駄文筆者に、某TV局から電話があった。内容は、某官庁の後援でエネルギー問題に関して大学生達の討議によるシンポジウムが計画されているので、討議に参加する学生を推薦して欲しいという依頼であった。駄文筆者は、環境法を熱心に学んでいる法学部性を知っていたので、指導教授および本人の承諾を得て推薦した。
シンポジウムの当日、駄文筆者は客席で観覧した。各大学から推薦された学生達は、概して真摯に議論していた。その中で、駄文筆者が推薦した学院性は、建物等のライト・アップは必要性が乏しいから止めるべきではないか、という問題提起を行った。これに対して、司会を務めていた官僚は、「あれは、最初から予算化されているので、いいんです」と述べて、この問題提起を無視した。エネルギー・資源・環境を論じている筈なのに、予算化を理由として論題にしないという論点齟齬に、駄文筆者は強い違和感を覚えた。
後日、シンポジウムの録画がTVで放送された。これを見て、駄文筆者の違和感は不信感に変化した。ライト・アップに関する発言が、削除されていたのである。他大学学生によるウケ狙いの愚劣な発言は一部だけの削除に留まっていたのに、ライト・アップに関する発言は全部削除だったのである。
問題提起の無視は「議論させない」という判断を示している。発言の削除は「人々に聞かせない」という判断を示している。「予算化」は税金から関係業界への支出の保証である。「議論させない」「聞かせない」という判断が如何なる理由に基づくのか、駄文筆者は情報を得ていないが、関係業界の利潤を絶対的優先事項とするなら、疑念を抱く人もあり得る。逆に言えば、議論させず聞かせないことは、疑念の抑制になる。意図的ではないとしても、そのような効果は否定できない。
ライト・アップ擁護論として、LEDを使用するから電力消費は少ないという主張がある。しかし、ライト・アップ反対論は電力使用の必要性がないという主張であって使用量の多寡を問題にしている訳ではない。電力使用の必要性を論じることなく使用量が少ないからよいと主張することは、論点齟齬の誤謬である
ライト・アップについては、植物への悪影響を懸念する見解も存在する由である。駄文筆者は正確な知識を持っておらず、因果関係の有無も判らないが、某観光地に関してライト・アップ開始後に紅葉の色が悪くなったという実感を抱いている。駄文筆者としては、これも懸念事項である。
ライト・アップは綺麗だという評価に異論を唱える意図は毛頭ない。多数の人々が喜んで鑑賞していること自体は悪いことではない。これに伴って金銭が動くことも、直ちに悪だと評価できる訳ではない。しかし、電力使用に値するのかという利害得失の比較衡量を尽くすことなくライト・アップ実施を絶対視するなら、駄文筆者は疑念を覚えざるを得ない。陰謀論ジジイになり下がった駄文筆者は、戯言を呟く。
「ライト・アップの背後には、巨大な闇がある。」
(令7・1・25)
平成初期の話である。当時まだ愛知学院大学法学部教授であった駄文筆者に、某TV局から電話があった。内容は、某官庁の後援でエネルギー問題に関して大学生達の討議によるシンポジウムが計画されているので、討議に参加する学生を推薦して欲しいという依頼であった。駄文筆者は、環境法を熱心に学んでいる法学部性を知っていたので、指導教授および本人の承諾を得て推薦した。
シンポジウムの当日、駄文筆者は客席で観覧した。各大学から推薦された学生達は、概して真摯に議論していた。その中で、駄文筆者が推薦した学院性は、建物等のライト・アップは必要性が乏しいから止めるべきではないか、という問題提起を行った。これに対して、司会を務めていた官僚は、「あれは、最初から予算化されているので、いいんです」と述べて、この問題提起を無視した。エネルギー・資源・環境を論じている筈なのに、予算化を理由として論題にしないという論点齟齬に、駄文筆者は強い違和感を覚えた。
後日、シンポジウムの録画がTVで放送された。これを見て、駄文筆者の違和感は不信感に変化した。ライト・アップに関する発言が、削除されていたのである。他大学学生によるウケ狙いの愚劣な発言は一部だけの削除に留まっていたのに、ライト・アップに関する発言は全部削除だったのである。
問題提起の無視は「議論させない」という判断を示している。発言の削除は「人々に聞かせない」という判断を示している。「予算化」は税金から関係業界への支出の保証である。「議論させない」「聞かせない」という判断が如何なる理由に基づくのか、駄文筆者は情報を得ていないが、関係業界の利潤を絶対的優先事項とするなら、疑念を抱く人もあり得る。逆に言えば、議論させず聞かせないことは、疑念の抑制になる。意図的ではないとしても、そのような効果は否定できない。
ライト・アップ擁護論として、LEDを使用するから電力消費は少ないという主張がある。しかし、ライト・アップ反対論は電力使用の必要性がないという主張であって使用量の多寡を問題にしている訳ではない。電力使用の必要性を論じることなく使用量が少ないからよいと主張することは、論点齟齬の誤謬である
ライト・アップについては、植物への悪影響を懸念する見解も存在する由である。駄文筆者は正確な知識を持っておらず、因果関係の有無も判らないが、某観光地に関してライト・アップ開始後に紅葉の色が悪くなったという実感を抱いている。駄文筆者としては、これも懸念事項である。
ライト・アップは綺麗だという評価に異論を唱える意図は毛頭ない。多数の人々が喜んで鑑賞していること自体は悪いことではない。これに伴って金銭が動くことも、直ちに悪だと評価できる訳ではない。しかし、電力使用に値するのかという利害得失の比較衡量を尽くすことなくライト・アップ実施を絶対視するなら、駄文筆者は疑念を覚えざるを得ない。陰謀論ジジイになり下がった駄文筆者は、戯言を呟く。
「ライト・アップの背後には、巨大な闇がある。」
(令7・1・25)