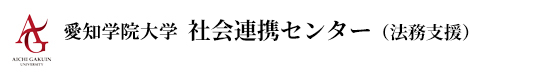有罪自認事件への対応
愛知学院大学名誉教授・弁護士 原田保
刑事被告事件の大部分は有罪自認事件である。被告人側が争うことなく有罪を自認すると、大抵は起訴状通りの有罪判決が宣告される。被告人は受け入れ、検査官は満足し、裁判官は検討を省略して迅速に処理できる。しかし、それは必ずしも適正な裁判ではない。
このような有罪判決においては、しばしば、犯罪事実に関して適法な証拠に基づいて合理的疑いを超える証明が尽くされておらず、あるいは、犯罪成立を導く論理の誤謬・欠落が放置されている。これでは犯罪が証明されたと認めることができない。有罪判決に関する刑事訴訟法336条1項には「犯罪の証明があったとき」と規定されているが、このような有罪判決が是認されるなら、事実上の運用は「被告人側が争わなかったとき」である。法令に違反しており、適正な裁判ではない。
そもそも、被告人側が有罪を自認するのは、必ずしも納得しているからではない。検察官主張の問題点に気付いていないなら弁護人も検察官と同罪であるが、気付いていても反論しないことがある。被告人が反論による裁判長期化を回避したいと考えるこは、珍しくない。とりわけ、勾留によって耐え難い生活破壊被を被り、争うと保釈されない、刑は罰金で済む、自由刑でも執行猶予が期待できる、という場合には、納得できない有罪判決を受忍してでも即時の日常生活復帰を念願する例が少なくない。人質司法は強い。弁護人は被告人の意向を無視し難く、説得にも限界がある。
それでも、被告人側の反論がなくても、検察官主張の問題点を糺すことが裁判官の職責である。しかし、「常に優しく検察官に寄り添う裁判官」は、検察官主張を無批判に認容する。
こうして、欠陥判例が形成される。詳論は略すが、死体があれば直ちに死体遺棄罪であるとか、暴行が複数回に亘ればそれだけで常習暴行罪が成立するとか、誤った法適用の例は少なくない。試験での不正行為が偽計業務妨害罪とされた少年審判の例もある。広島原爆ドーム立入事件の建造物侵入罪不成立や令5・4・3ブログ(ブログ集vol.7(令6)2頁)で寸評した熊本死産児遺棄事件の死体遺棄罪罪不成立は、弁護人の適切な反論が奏功した貴重な例である。なお、広島原爆ドーム立入事件の弁護人は、令5・4・12ブログ(ブログ集vol.7(令6)4頁)で紹介した阿波弘夫弁護士である。
共犯者間で争うか否かの判断が分かれた場合には、更に重大な問題が生じる。このような場合には分離公判となるが、大抵は同一裁判官が担当する。その裁判官が有罪自認被告人に対して有罪判決を宣告したなら、争う被告人に対する無罪判決は同一人物の行為として矛盾であり、先に宣告した有罪判決に対する再審請求や非常上告上申が予測される。
駄文筆者の経験によれば、先に宣告した有罪判決を自ら否定した裁判官は見当たらず、想像を絶する詭弁を弄して先に宣告した有罪判決との一貫性を維持しようとした裁判官は実在する。共犯事件における有罪自認は、無罪を主張する共犯者を有罪にする行為なのである。
以上に述べたように、「常に優しく検察官に寄り添う裁判が」が存在する限り、公正な裁判は期待し難い。同一裁判官による分離公判については、忌避や除斥が検討れるべきである。
(令7・3・14)
刑事被告事件の大部分は有罪自認事件である。被告人側が争うことなく有罪を自認すると、大抵は起訴状通りの有罪判決が宣告される。被告人は受け入れ、検査官は満足し、裁判官は検討を省略して迅速に処理できる。しかし、それは必ずしも適正な裁判ではない。
このような有罪判決においては、しばしば、犯罪事実に関して適法な証拠に基づいて合理的疑いを超える証明が尽くされておらず、あるいは、犯罪成立を導く論理の誤謬・欠落が放置されている。これでは犯罪が証明されたと認めることができない。有罪判決に関する刑事訴訟法336条1項には「犯罪の証明があったとき」と規定されているが、このような有罪判決が是認されるなら、事実上の運用は「被告人側が争わなかったとき」である。法令に違反しており、適正な裁判ではない。
そもそも、被告人側が有罪を自認するのは、必ずしも納得しているからではない。検察官主張の問題点に気付いていないなら弁護人も検察官と同罪であるが、気付いていても反論しないことがある。被告人が反論による裁判長期化を回避したいと考えるこは、珍しくない。とりわけ、勾留によって耐え難い生活破壊被を被り、争うと保釈されない、刑は罰金で済む、自由刑でも執行猶予が期待できる、という場合には、納得できない有罪判決を受忍してでも即時の日常生活復帰を念願する例が少なくない。人質司法は強い。弁護人は被告人の意向を無視し難く、説得にも限界がある。
それでも、被告人側の反論がなくても、検察官主張の問題点を糺すことが裁判官の職責である。しかし、「常に優しく検察官に寄り添う裁判官」は、検察官主張を無批判に認容する。
こうして、欠陥判例が形成される。詳論は略すが、死体があれば直ちに死体遺棄罪であるとか、暴行が複数回に亘ればそれだけで常習暴行罪が成立するとか、誤った法適用の例は少なくない。試験での不正行為が偽計業務妨害罪とされた少年審判の例もある。広島原爆ドーム立入事件の建造物侵入罪不成立や令5・4・3ブログ(ブログ集vol.7(令6)2頁)で寸評した熊本死産児遺棄事件の死体遺棄罪罪不成立は、弁護人の適切な反論が奏功した貴重な例である。なお、広島原爆ドーム立入事件の弁護人は、令5・4・12ブログ(ブログ集vol.7(令6)4頁)で紹介した阿波弘夫弁護士である。
共犯者間で争うか否かの判断が分かれた場合には、更に重大な問題が生じる。このような場合には分離公判となるが、大抵は同一裁判官が担当する。その裁判官が有罪自認被告人に対して有罪判決を宣告したなら、争う被告人に対する無罪判決は同一人物の行為として矛盾であり、先に宣告した有罪判決に対する再審請求や非常上告上申が予測される。
駄文筆者の経験によれば、先に宣告した有罪判決を自ら否定した裁判官は見当たらず、想像を絶する詭弁を弄して先に宣告した有罪判決との一貫性を維持しようとした裁判官は実在する。共犯事件における有罪自認は、無罪を主張する共犯者を有罪にする行為なのである。
以上に述べたように、「常に優しく検察官に寄り添う裁判が」が存在する限り、公正な裁判は期待し難い。同一裁判官による分離公判については、忌避や除斥が検討れるべきである。
(令7・3・14)