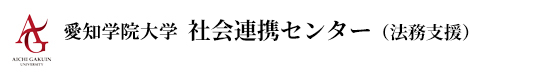確信犯は「敬意・優遇」の対象である!
愛知学院大学名誉教授・弁護士 原田保
「正しいと信じて」か「悪いと知りながら」かという無意味な論争を見る限り、確信犯という概念が提唱された理由を知らない人が少なくないと推測される。そこで、この点について略述する。
「政治、宗教等の確信に対する忠実に基づく犯罪は特殊な範疇である」とフランツ・リストが論じ、これに「確信犯」という名称をグスタフ・ラートブルフが付した。特殊な範疇の犯罪への対応如何という刑事政策の課題として提唱されたのである。
この特殊な犯罪への対応は、刑事施設収容中に「作業義務を課さない」という優遇である。理由は、「世のため人のため」あるいは「神の御心」だから遂行しなければならないという「崇高な」公益的義務感を動機とする犯罪者は、「道義的に国と対等」だから敬意を以て処遇するべきであり、私利私欲で他人の権利を侵害した通常の犯罪者のように国が上から懲らしめる対象ではない、と考えられたことである。異論も多々あるが、これが当時の思想であった。価値相対主義の反映と解することもできる。
こうして、多くの国々で、作業義務のある通常の自由刑と作業義務のない特別の自由刑との2種類が規定された。日本でも、明治13年の旧刑法で作業義務のある自由刑と作業義務のない自由刑との区別が規定され、これが明治40年の現行刑法における懲役・禁錮の区別に継受された。
以上の歴史的事実を前提に、「正しいと信じて」「悪いと知りながら」という文化庁が提示した選択肢の欠陥を指摘する。
「正しいと信じて」は、「正しい」の判断基準が示されていない。行為者独自の規範により正しいなら確信犯と矛盾しないとしても、国の現行法により正しいなら違法性の錯誤であって確信犯ではない。どちらであるのか特定できないから、「正解」とも「誤用」とも断言できない。
「悪いと知りながら」は、それでも遂行する動機が示されていない。公益的義務感が動機なら確信犯であるが、私利私欲が動機なら規範意識鈍麻であって確信犯ではない。どちらであるのか特定できないから、「正解」とも「誤用」とも断言できない。
このように、文化庁が提示した選択肢は、確信犯か否かの判断に必要な情報を欠いている。そもそも、公益的義務感という動機が確信犯の必須要素なのであるから、動機を明示しないことは致命的欠落であり、凡そ確信犯の説明になり得ない。このような選択肢を提示した人も、どちらかを躊躇なく選択した人も、確信犯の意味を理解していないことが明白である。
文化庁は「正しいと信じて」が正解だと述べ、これに同調する人の相当数は違法性の錯誤を論じている。「悪いと知りながら」が正解だと主張する人の相当数は規範意識鈍麻を論じている。どちらも非難として使用されており、本来の意味とは真逆である。確信犯概念が敬意・優遇の対象として提唱されたという歴史的事実を知らないからこその用法である。
言葉の意味は変遷するから、どちらも既に誤用から新用法に変化したのかもしれない。それでも、本来の意味と全く異なることに変わりはないから、「新用法として正しい意味」であるとしても「本来の正しい意味」ではない。昨今の「正しい意味」論争が「本来の正しい意味」を論じる意図なら、どちらも誤謬である。誤謬言説間の「正しい意味」論争は、無意味と評する他ない。尤も、懲役・禁錮の区別が廃止されたら、確信犯であることに基づく法効果が廃止されることになるから、本来の意味も消えるが。
(令7・4・15)
「正しいと信じて」か「悪いと知りながら」かという無意味な論争を見る限り、確信犯という概念が提唱された理由を知らない人が少なくないと推測される。そこで、この点について略述する。
「政治、宗教等の確信に対する忠実に基づく犯罪は特殊な範疇である」とフランツ・リストが論じ、これに「確信犯」という名称をグスタフ・ラートブルフが付した。特殊な範疇の犯罪への対応如何という刑事政策の課題として提唱されたのである。
この特殊な犯罪への対応は、刑事施設収容中に「作業義務を課さない」という優遇である。理由は、「世のため人のため」あるいは「神の御心」だから遂行しなければならないという「崇高な」公益的義務感を動機とする犯罪者は、「道義的に国と対等」だから敬意を以て処遇するべきであり、私利私欲で他人の権利を侵害した通常の犯罪者のように国が上から懲らしめる対象ではない、と考えられたことである。異論も多々あるが、これが当時の思想であった。価値相対主義の反映と解することもできる。
こうして、多くの国々で、作業義務のある通常の自由刑と作業義務のない特別の自由刑との2種類が規定された。日本でも、明治13年の旧刑法で作業義務のある自由刑と作業義務のない自由刑との区別が規定され、これが明治40年の現行刑法における懲役・禁錮の区別に継受された。
以上の歴史的事実を前提に、「正しいと信じて」「悪いと知りながら」という文化庁が提示した選択肢の欠陥を指摘する。
「正しいと信じて」は、「正しい」の判断基準が示されていない。行為者独自の規範により正しいなら確信犯と矛盾しないとしても、国の現行法により正しいなら違法性の錯誤であって確信犯ではない。どちらであるのか特定できないから、「正解」とも「誤用」とも断言できない。
「悪いと知りながら」は、それでも遂行する動機が示されていない。公益的義務感が動機なら確信犯であるが、私利私欲が動機なら規範意識鈍麻であって確信犯ではない。どちらであるのか特定できないから、「正解」とも「誤用」とも断言できない。
このように、文化庁が提示した選択肢は、確信犯か否かの判断に必要な情報を欠いている。そもそも、公益的義務感という動機が確信犯の必須要素なのであるから、動機を明示しないことは致命的欠落であり、凡そ確信犯の説明になり得ない。このような選択肢を提示した人も、どちらかを躊躇なく選択した人も、確信犯の意味を理解していないことが明白である。
文化庁は「正しいと信じて」が正解だと述べ、これに同調する人の相当数は違法性の錯誤を論じている。「悪いと知りながら」が正解だと主張する人の相当数は規範意識鈍麻を論じている。どちらも非難として使用されており、本来の意味とは真逆である。確信犯概念が敬意・優遇の対象として提唱されたという歴史的事実を知らないからこその用法である。
言葉の意味は変遷するから、どちらも既に誤用から新用法に変化したのかもしれない。それでも、本来の意味と全く異なることに変わりはないから、「新用法として正しい意味」であるとしても「本来の正しい意味」ではない。昨今の「正しい意味」論争が「本来の正しい意味」を論じる意図なら、どちらも誤謬である。誤謬言説間の「正しい意味」論争は、無意味と評する他ない。尤も、懲役・禁錮の区別が廃止されたら、確信犯であることに基づく法効果が廃止されることになるから、本来の意味も消えるが。
(令7・4・15)