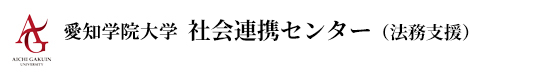公費解体後の更地の処分について
愛知学院大学特別教授・弁護士 國田武二郎
Q:先祖から引き継がれた実家は震災で全損となり公費で解体されました。現在は、更地(約80坪)の状態です。既に70歳で今さら、新築する資金も気力もありません。子ども達も、都会に出て田舎には戻らないと言っています。私も妻も、余生を子ども達のいる都会に一緒に過ごそうと考えています。しかし、更地のままの状態では、固定資産税はかかり、また、草も時々刈る必要があると思うと気が重くなります。2023年4月から相続で取得した土地を手放して国有地とする制度が始まったと聞きましたが、どんな制度でしょうか。
A:設問の制度は「相続土地国庫帰属制度」というもので、父母から相続した実家の土地を国に引き取ってもらう制度です。この制度については、既にこの欄(2024年版8月号)でも説明していますが、それも参照しながらもう少し解説します。この制度が始まり、令和7年1月末現在で所有権が国に移った土地は,申請3343件中、1324件です。対象は、相続か、相続人への遺贈によって取得した土地に限られ、引き取った土地は国民の税金で管理することになるため、過大な費用や労力がかかる土地は認められず、管理費として一定の負担金を国に納める必要があります。しかし、申請しても却下・不承認となる土地としては①建物が存在する。➁担保権や、使用・収益を目的とする権利が設定されている。➂通路、墓地、水道用地など他人により使用されている。④汚染されている。⑤境界が明らかでない。⑥崖があり、管理に過分の費用や労力が必要である。⑦管理や処分を阻害する工作物や車両、樹木などがある。⑧適切な間伐などがされず、整備が追加で必要な森林である。などです。
そこで、国が引き取ってもらえる土地かどうか、その見込みを申請前に知りたいならば、写真や資料を持って法務局に相談すればよいと思います。土地の範囲が明確でない場合、自分で認識している範囲を杭や鋲など目印になるものを設けて示せば、法務局で改めて調べてくれます。法務局への申請手数料は一律1万4千円で、しばらくして、「受入れ決定」の連絡決定がきます。その後は、10年分の国による管理費として算出された負担金を納付すれば国のものとなり、国から「財産を引き受けました」旨の書面が届き、これで、祖先から引き継がれた土地の所有権は国に移ります。
国に納める負担金ですが、①宅地は面積にかかわらず20万円(但し、市街化区域など一部の市街地は、面積に応じて算定)、➁田畑は面積にかかわらず20万円(但し、農用地区域などは面積に応じて算定)、➂森林は面積に応じて算定(1500㎡で約27万円、3000㎡で約30万円)、④その他(雑種地、原野など)は、面積にかかわらず20万円です。
負担金が高い、引取りの条件が厳しいという声もありますが、引き取った後は、国としても、国民の税金で管理していかなければならないので、仕方ないのかもしれません。もっとも、開始から5年経過後に、必要があれば制度を見直すということになっているので、場合によっては、引取りなどの要件は緩和される可能性があるかもしれません。自分が亡くなった後、田舎の土地について妻子に負担をかけたくないと思われている方は、一度、この制度を検討してみてはいかがでしょうか。
(AGULS96号(2025/07/25)掲載)
Q:先祖から引き継がれた実家は震災で全損となり公費で解体されました。現在は、更地(約80坪)の状態です。既に70歳で今さら、新築する資金も気力もありません。子ども達も、都会に出て田舎には戻らないと言っています。私も妻も、余生を子ども達のいる都会に一緒に過ごそうと考えています。しかし、更地のままの状態では、固定資産税はかかり、また、草も時々刈る必要があると思うと気が重くなります。2023年4月から相続で取得した土地を手放して国有地とする制度が始まったと聞きましたが、どんな制度でしょうか。
A:設問の制度は「相続土地国庫帰属制度」というもので、父母から相続した実家の土地を国に引き取ってもらう制度です。この制度については、既にこの欄(2024年版8月号)でも説明していますが、それも参照しながらもう少し解説します。この制度が始まり、令和7年1月末現在で所有権が国に移った土地は,申請3343件中、1324件です。対象は、相続か、相続人への遺贈によって取得した土地に限られ、引き取った土地は国民の税金で管理することになるため、過大な費用や労力がかかる土地は認められず、管理費として一定の負担金を国に納める必要があります。しかし、申請しても却下・不承認となる土地としては①建物が存在する。➁担保権や、使用・収益を目的とする権利が設定されている。➂通路、墓地、水道用地など他人により使用されている。④汚染されている。⑤境界が明らかでない。⑥崖があり、管理に過分の費用や労力が必要である。⑦管理や処分を阻害する工作物や車両、樹木などがある。⑧適切な間伐などがされず、整備が追加で必要な森林である。などです。
そこで、国が引き取ってもらえる土地かどうか、その見込みを申請前に知りたいならば、写真や資料を持って法務局に相談すればよいと思います。土地の範囲が明確でない場合、自分で認識している範囲を杭や鋲など目印になるものを設けて示せば、法務局で改めて調べてくれます。法務局への申請手数料は一律1万4千円で、しばらくして、「受入れ決定」の連絡決定がきます。その後は、10年分の国による管理費として算出された負担金を納付すれば国のものとなり、国から「財産を引き受けました」旨の書面が届き、これで、祖先から引き継がれた土地の所有権は国に移ります。
国に納める負担金ですが、①宅地は面積にかかわらず20万円(但し、市街化区域など一部の市街地は、面積に応じて算定)、➁田畑は面積にかかわらず20万円(但し、農用地区域などは面積に応じて算定)、➂森林は面積に応じて算定(1500㎡で約27万円、3000㎡で約30万円)、④その他(雑種地、原野など)は、面積にかかわらず20万円です。
負担金が高い、引取りの条件が厳しいという声もありますが、引き取った後は、国としても、国民の税金で管理していかなければならないので、仕方ないのかもしれません。もっとも、開始から5年経過後に、必要があれば制度を見直すということになっているので、場合によっては、引取りなどの要件は緩和される可能性があるかもしれません。自分が亡くなった後、田舎の土地について妻子に負担をかけたくないと思われている方は、一度、この制度を検討してみてはいかがでしょうか。
(AGULS96号(2025/07/25)掲載)