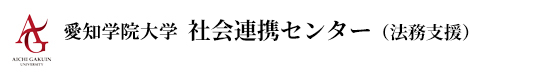撒骨(散骨)の法的評価に関する認識状況 [撒骨・その16]
愛知学院大学名誉教授・弁護士 原田保
令和7年6月14日に愛知学院大学名城公園キャンパスで開催された宗教法学会において、「新しい葬法の法的評価」と題するシンポジウムが行われた。その際に判った事実および望まれる対応について述べる。
まず、シンポジウムでは、
①撒骨に係る遺骨遺棄罪成否に関する国の見解は未だ示されていない。
②撒骨に係る遺骨遺棄罪は当然に不成立であって検討を要しない。
という共通認識が示されていた。
①は質疑応答で判った。撒骨に係る遺骨遺棄罪成否に関する国の見解如何という質問に対して判例がなく未だ決まっていない旨の回答があり、この回答に対する異論はなかった。
この事実は、撒骨の法的評価が国としては未解決問題である旨の共通認識を示している。それは「遺骨遺棄罪不成立を国が認めた」という撒骨業者・撒骨推進団体の言説を学会の専門家が否定したことを意味する。
②は報告内容で判った。報告論題とされた新葬法は撒骨だけで、報告内容は専ら行政規制であった。手元供養やゼロ葬が報告論題とされなかったのは、行政規制の動向が見当たらないからだと推測できる。
犯罪は処罰の対象であって行政規制の対象ではないから、行政規制は現行法上の犯罪が成立しないことを前提とする。遺骨遺棄罪成否如何を全く論じることなく行政規制を論じるシンポジウムは、遺骨遺棄罪不成立が議論不要の明白な結論であるという共通認識を示している。
以上の事実につき、望まれる対応は下記の通りである。
①については、撒骨の法的評価に関する国の有権的解釈が存在しないという真実が、学会の共通認識であっても、一般に周知されていない点に問題がある。そして、現在の多数意見たる散骨賛成論が国の公認という印象に誘導されていることも、国の公認が存在しないことを知ると賛成論から反対論に転向する人がいることも、証明済である。誤信に基づく多数意見は、法適用の前提たる社会通念ではなく、排斥するべき迷妄である。適切な評価には誤信のない社会通念を要するから、国の公認は存在しないという真実を知って、撒骨の適否および悲嘆・嫌忌に関する受忍義務の存否を検討し、法適用の前提たり得る社会通念を形成するべきである。
そのためには、正しい情報の周知によるデマ払拭が必要である。駄文筆者の発信だけでは足らず、テレビ・ラジオ・新聞・週刊誌・SNS等々による真実伝達を要する。多様な媒体による真実情報の拡散を期待する。とりわけ「葬送の自由をすすめる会」創始者の勤務先であった朝日新聞は、同会会員と思しき法務官僚個人の撒骨適法説を「法務省公式見解」と報じて同会が発信したデマを広範に拡散させた責任者であるから、デマ払拭に献身する義務を負う筈である。報道機関の責務履行を切望する。
②については、新葬法に係る刑法犯成否を検討する必要性が撒骨業者・撒骨推進団体だけでなく学会でも認識されていない現状への対応方法を検討しなければならない。
駄文筆者は、撒骨に係る遺骨遺棄罪成立を主張して撒骨適法説を批判してきた。行政規制を論じる人は同罪不成立を前提としている筈であるが、駄文筆者の言説に対する反論は見当たらない。関心を持たれないと判断できる。それは駄文筆者の責任であるが、このままでは撒骨業者・撒骨推進団体は虚構の権威に安住し続け、葬送の無法地帯化が危惧される。撒骨違法説の存在・内容が周知されるよう、一層の努力を要する。
(令7・10・21)
令和7年6月14日に愛知学院大学名城公園キャンパスで開催された宗教法学会において、「新しい葬法の法的評価」と題するシンポジウムが行われた。その際に判った事実および望まれる対応について述べる。
まず、シンポジウムでは、
①撒骨に係る遺骨遺棄罪成否に関する国の見解は未だ示されていない。
②撒骨に係る遺骨遺棄罪は当然に不成立であって検討を要しない。
という共通認識が示されていた。
①は質疑応答で判った。撒骨に係る遺骨遺棄罪成否に関する国の見解如何という質問に対して判例がなく未だ決まっていない旨の回答があり、この回答に対する異論はなかった。
この事実は、撒骨の法的評価が国としては未解決問題である旨の共通認識を示している。それは「遺骨遺棄罪不成立を国が認めた」という撒骨業者・撒骨推進団体の言説を学会の専門家が否定したことを意味する。
②は報告内容で判った。報告論題とされた新葬法は撒骨だけで、報告内容は専ら行政規制であった。手元供養やゼロ葬が報告論題とされなかったのは、行政規制の動向が見当たらないからだと推測できる。
犯罪は処罰の対象であって行政規制の対象ではないから、行政規制は現行法上の犯罪が成立しないことを前提とする。遺骨遺棄罪成否如何を全く論じることなく行政規制を論じるシンポジウムは、遺骨遺棄罪不成立が議論不要の明白な結論であるという共通認識を示している。
以上の事実につき、望まれる対応は下記の通りである。
①については、撒骨の法的評価に関する国の有権的解釈が存在しないという真実が、学会の共通認識であっても、一般に周知されていない点に問題がある。そして、現在の多数意見たる散骨賛成論が国の公認という印象に誘導されていることも、国の公認が存在しないことを知ると賛成論から反対論に転向する人がいることも、証明済である。誤信に基づく多数意見は、法適用の前提たる社会通念ではなく、排斥するべき迷妄である。適切な評価には誤信のない社会通念を要するから、国の公認は存在しないという真実を知って、撒骨の適否および悲嘆・嫌忌に関する受忍義務の存否を検討し、法適用の前提たり得る社会通念を形成するべきである。
そのためには、正しい情報の周知によるデマ払拭が必要である。駄文筆者の発信だけでは足らず、テレビ・ラジオ・新聞・週刊誌・SNS等々による真実伝達を要する。多様な媒体による真実情報の拡散を期待する。とりわけ「葬送の自由をすすめる会」創始者の勤務先であった朝日新聞は、同会会員と思しき法務官僚個人の撒骨適法説を「法務省公式見解」と報じて同会が発信したデマを広範に拡散させた責任者であるから、デマ払拭に献身する義務を負う筈である。報道機関の責務履行を切望する。
②については、新葬法に係る刑法犯成否を検討する必要性が撒骨業者・撒骨推進団体だけでなく学会でも認識されていない現状への対応方法を検討しなければならない。
駄文筆者は、撒骨に係る遺骨遺棄罪成立を主張して撒骨適法説を批判してきた。行政規制を論じる人は同罪不成立を前提としている筈であるが、駄文筆者の言説に対する反論は見当たらない。関心を持たれないと判断できる。それは駄文筆者の責任であるが、このままでは撒骨業者・撒骨推進団体は虚構の権威に安住し続け、葬送の無法地帯化が危惧される。撒骨違法説の存在・内容が周知されるよう、一層の努力を要する。
(令7・10・21)