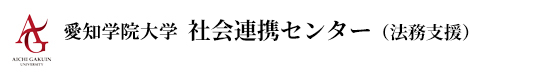第三者委員会について
愛知学院大学教授・弁護士 浅賀哲
最近、第三者委員会が注目されております。
組織内の不祥事が生じた際にその自浄作用によって問題を解決することができないときに、外部の専門家によって構成される第三者委員会が事実関係を調査し、不祥事の是正、再発防止の提言等をして、問題解決にあたることがあります。有名なものとしては、宝塚事件、関西電力事件、フジテレビの事件、兵庫県知事のパワーハラスメント事件等があります。
フジテレビの事件は、みなさまの記憶に新しいところでしょうが、男性タレントがフジテレビの女性社員に対して、不法行為を働いたにもかかわらず、その後も番組起用するなどの一連のフジテレビの対応が問題となり、CM取引が多数解約となり、フジテレビの企業価値を毀損したというものです。
本来、企業においては、組織として自らが違法行為、不適切を行為に対応して、自浄作用として適法な状態に戻すべきであり、そのため、社外役員等からなる取締役会、監査役会が中心となるガバナンスの仕組みがあります。ところが、企業のトップ層に歪みが生じていたり、企業風土に長年の問題があるときには、自浄作用が発揮できないことも少なくありません。そこで、日本独自の制度として、第三者委員会が発達しました。第三者委員会は山一証券の破綻事件の際に最初に設置されたといわれ、その後、日本弁護士連合会においてガイドラインが作成され、実務的にも定着しました。
この点、日本弁護士連合会のガイドラインに沿った第三者委員会なのか、内部調査委員会なのかという点が、例えば宝塚事件においては大きく問題とされ、委員会の構成員について、注目を浴びることがあります。委員会の構成員が企業から独立した「第三者」なのか否かというのは、報告書を検討するにあたって、一つのポイントとなります。どうしても、内部調査である場合には、手心を加えたのではないかという疑念が払拭されないことあります。
また、第三者委員会の提言を会社が真摯に受け止め、実行をするか、否かにも、注目がなされております。この点に関しては、ジャニーズ事件などが参考となります。
さらに、第三者委員会の事実認定が関係者の任意の協力の下、短期間での作業においてなされるため完全ではないことから、事後の裁判において事実認定が覆るということも多々起きており、第三者委員会は新たな局面を迎えております。
しかしながら、第三者委員会は、企業・地方自治体等の組織の再出発をなす社会的な機能・期待は大きく、今後も注目される制度であるので、取り上げさせていただきました。みなさんも、第三者委員会について報道等に触れた際には、上記の点を踏まえながら、ご検討をいただければと存じます。
(AGULS99号(2025/10/25)掲載)
最近、第三者委員会が注目されております。
組織内の不祥事が生じた際にその自浄作用によって問題を解決することができないときに、外部の専門家によって構成される第三者委員会が事実関係を調査し、不祥事の是正、再発防止の提言等をして、問題解決にあたることがあります。有名なものとしては、宝塚事件、関西電力事件、フジテレビの事件、兵庫県知事のパワーハラスメント事件等があります。
フジテレビの事件は、みなさまの記憶に新しいところでしょうが、男性タレントがフジテレビの女性社員に対して、不法行為を働いたにもかかわらず、その後も番組起用するなどの一連のフジテレビの対応が問題となり、CM取引が多数解約となり、フジテレビの企業価値を毀損したというものです。
本来、企業においては、組織として自らが違法行為、不適切を行為に対応して、自浄作用として適法な状態に戻すべきであり、そのため、社外役員等からなる取締役会、監査役会が中心となるガバナンスの仕組みがあります。ところが、企業のトップ層に歪みが生じていたり、企業風土に長年の問題があるときには、自浄作用が発揮できないことも少なくありません。そこで、日本独自の制度として、第三者委員会が発達しました。第三者委員会は山一証券の破綻事件の際に最初に設置されたといわれ、その後、日本弁護士連合会においてガイドラインが作成され、実務的にも定着しました。
この点、日本弁護士連合会のガイドラインに沿った第三者委員会なのか、内部調査委員会なのかという点が、例えば宝塚事件においては大きく問題とされ、委員会の構成員について、注目を浴びることがあります。委員会の構成員が企業から独立した「第三者」なのか否かというのは、報告書を検討するにあたって、一つのポイントとなります。どうしても、内部調査である場合には、手心を加えたのではないかという疑念が払拭されないことあります。
また、第三者委員会の提言を会社が真摯に受け止め、実行をするか、否かにも、注目がなされております。この点に関しては、ジャニーズ事件などが参考となります。
さらに、第三者委員会の事実認定が関係者の任意の協力の下、短期間での作業においてなされるため完全ではないことから、事後の裁判において事実認定が覆るということも多々起きており、第三者委員会は新たな局面を迎えております。
しかしながら、第三者委員会は、企業・地方自治体等の組織の再出発をなす社会的な機能・期待は大きく、今後も注目される制度であるので、取り上げさせていただきました。みなさんも、第三者委員会について報道等に触れた際には、上記の点を踏まえながら、ご検討をいただければと存じます。
(AGULS99号(2025/10/25)掲載)