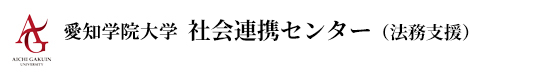時効制度の趣旨
愛知学院大学教授 (刑事法) 原田 保
周知されていないように見受けられるので、述べておく。司法試験では、たぶん要らない。
「時効」という言葉は「公訴時効」の意味で使用されることが多いようだが、刑事では公訴時効の他に刑の時効があり、民法その他の法分野にも時効制度がある。また、日本独自の制度だと信じている人に遭遇したことがあるが、地球上で普遍的な制度である。
一言で説明すると、「長期間継続した事実状態を法的に固定する」のが時効制度である。「時の重み」に基づく制度である。本来の権利義務が実現されないまま長期間継続した事実状態を法的に固定するべく、存在していた権利を失わせたり (消滅時効)、存在しなかった権利を作ったり (取得時効) するのである。刑事では、訴追・刑執行が行われない事実状態が長期間継続したら、国家刑罰権を消滅させて訴追・刑執行を法的に不可能にするのである。
このような制度が何故あるのか。この点について、誤解や不十分な説明が見受けられる。
長期間の経過による証拠散逸が指摘される。経験則上あり得る事態だが、証拠がなければ権利義務の実現は裁判上不可能だから、時効を俟つまでもない。逆に、証拠があっても時効が成立すれば権利義務は消滅するのだから、これは証拠如何の問題ではない。
権利の上に眠る者は保護されないという言葉もある。これも、妥当する事案が少なからず想定できる。しかし、権利義務実現の努力を続けていても、中断・停止の事由がなければ時効により実現不可能になるのだから、眠っていたことは必ずしも理由にならない。
このように、証拠散逸も権利放置も、そのような場合がままあるという程度のものであって、制度自体の十分な説明ではない。公訴時効完成を迎えた犯罪者は長期間の逃亡生活によって十分に罰せられているとの言辞に至っては、凡そ説明にならない論外の妄説である。
制度の趣旨・理由は、制度の内容と合致していなければならない。時効期間は権利義務の内容や刑の軽重によって区別されている。このような規定から、権利義務の内容や刑の軽重とそれが実現されないまま経過した期間の長短との比較衡量が看取される。
法的な権利義務は本来当然に実現されるべきである。しかし、本来の権利義務が実現されないままの不当な状態でも、それが長期間継続すると、人々はその事実状態を前提として行動し、その事実状態を前提として他の人々と様々な関係を取り結ぶ。そのような状況で本来の権利義務を実現しようとすると、長期間継続した事実状態に基づいて形成された現存の人間関係・生活状態を、突如として破壊することになる。
それでも本来の権利義務を実現するべきだ、ということは、勿論ある。身内から犯罪者が出て一家全員破滅という事態は珍しくもない。しかし、事件直後ではなく長期間経過後になると、今更そこまでするべきではない、と考えられる場合もあり得る。この考えを是認するなら、「現存の諸関係を破壊してでも実現するべき権利義務なのか」という判断を要することになる。迅速処理を要する場面では、権利が比較的短期間で時効により消滅する。重い罪・重い刑なら現存の諸関係を破壊することになっても訴追・執行しなければならないが、軽い罪・軽い刑なら現存の諸関係の方を優先させて訴追・執行を断念する。権利義務の重みと時の重みとの比較衡量である。この比較衡量に基づいて社会的安定を図るのが、時効制度なのである。
勿論、法律上の諸制度を批判することは自由であり、時効制度廃止論も立法論として成立可能である。しかし、制度の趣旨に関する誤解があると、適切な議論にならない。
刑事において、「被害者や遺族に時効はない」との言葉がしばしば発せられる。それは正しい。無関係な他人や加害者・債務者は忘れても、被害者・債権者やその遺族は忘れないことが多い。
しかし、これを時効制度批判の根拠にすると、論点齟齬に陥る。このブログで過去に述べたように、刑罰は被害者や遺族のための復讐代行制度ではない。被害者の権利として犯人処罰を論じると、真に必要な被害者支援を失念させて犯人死亡事案の被害者を無視するだけでなく、刑事法の歪曲をも生じさせる。被害者や遺族の意向を根拠とする公訴時効廃止論も、その一例である。
犯人が如何に悪辣な行為をしたか、被害者が如何に悲惨な目に遭ったか、という事実を公的に確認することは、被害者支援の一環として重要事項である。刑事被告事件裁判が行われないためにこのような公的確認が行われないという状態は、被害者支援に欠ける。しかし、それは公訴時効完成事案だけではない。公訴時効未完成でも、犯人が死亡すれば刑事被告事件判決は宣告されないから、犯罪や被害の内容・程度を公的に確認する機会は失われる。この点で、犯人死亡事案の被害者は公訴時効完成事案の被害者と同じ状態にある。
公訴時効廃止をかかる状態の解消手段と位置付ける主張は、同じ状態にある犯人死亡事案の被害者を無視している。被害者支援策は、公訴時効完成事案にも犯人死亡事案にも対応できるものでなければならない。
では、公訴時効廃止と共に、犯人死亡事案でも刑事被告事件裁判を可能にするべきなのか。再審は被告人が死亡しても遂行されるが、それは誤って犯人とされた人の雪冤を目的とする制度だからである。通常手続でそのような文字通りの「被告人抜き裁判」は刑事被告事件裁判にならない。刑事被告事件裁判は「この被告人をどうするべきか」を論題とする制度だから、論題たる被告人がいなければ無意味であると共に、被害者を少なくとも直接的には論題とするものではない。だから、「この被害者のためにどうするべきか」を論題とするなら、刑事被告事件裁判とは別の制度として、純粋に被害者支援のための制度を構築するべきなのである。
そして、公訴時効を廃止しても、犯人処罰は保証されない。15年間捜査して公訴提起できなかった事件が更に30年を経て被疑者・証拠の確保に至ることは、ほぼ期待不可能である。150年を経て奇跡的に犯人が特定できても、終局は被疑者死亡による不起訴である。被疑事件終局がなければ永久に被疑事件であり続けるから、200年前の殺人事件に関する捜査もあり得ることになる。しかし、関係者全員死亡が明白な昔の事件を被疑事件として捜査することは、現実に行われるとは考え難く、刑事司法の趣旨から外れる。故に、被疑事件を閉じることなく永久に放置するか、人間の生命の限界を超えた頃に氏名不詳被疑者死亡と判断して終局にするか、どちらかしかない。いずれにしても刑事司法完遂にならない。例えば崇峻天皇暗殺事件の真相解明は、今上天皇陛下の御要望があっても、刑事司法ではなく歴史学に適する事項である。
刑事司法の目標が犯人処罰である限り、公訴時効の延長は制度趣旨の範囲に留まり得るが、廃止は無意味・矛盾である。詳論は省略するが、公訴時効廃止は刑事司法完遂よりも「永久に許さない」旨の態度表明という政治的色彩の方が濃い。
公訴時効に限らず、時効制度をどうするかは、本来の権利義務を長期間経過後でも実現できるようにすることが、誰に如何なる利益をもたらすか、誰に如何なる損失をもたらすか、という点を熟慮して決するべき事柄である。
周知されていないように見受けられるので、述べておく。司法試験では、たぶん要らない。
「時効」という言葉は「公訴時効」の意味で使用されることが多いようだが、刑事では公訴時効の他に刑の時効があり、民法その他の法分野にも時効制度がある。また、日本独自の制度だと信じている人に遭遇したことがあるが、地球上で普遍的な制度である。
一言で説明すると、「長期間継続した事実状態を法的に固定する」のが時効制度である。「時の重み」に基づく制度である。本来の権利義務が実現されないまま長期間継続した事実状態を法的に固定するべく、存在していた権利を失わせたり (消滅時効)、存在しなかった権利を作ったり (取得時効) するのである。刑事では、訴追・刑執行が行われない事実状態が長期間継続したら、国家刑罰権を消滅させて訴追・刑執行を法的に不可能にするのである。
このような制度が何故あるのか。この点について、誤解や不十分な説明が見受けられる。
長期間の経過による証拠散逸が指摘される。経験則上あり得る事態だが、証拠がなければ権利義務の実現は裁判上不可能だから、時効を俟つまでもない。逆に、証拠があっても時効が成立すれば権利義務は消滅するのだから、これは証拠如何の問題ではない。
権利の上に眠る者は保護されないという言葉もある。これも、妥当する事案が少なからず想定できる。しかし、権利義務実現の努力を続けていても、中断・停止の事由がなければ時効により実現不可能になるのだから、眠っていたことは必ずしも理由にならない。
このように、証拠散逸も権利放置も、そのような場合がままあるという程度のものであって、制度自体の十分な説明ではない。公訴時効完成を迎えた犯罪者は長期間の逃亡生活によって十分に罰せられているとの言辞に至っては、凡そ説明にならない論外の妄説である。
制度の趣旨・理由は、制度の内容と合致していなければならない。時効期間は権利義務の内容や刑の軽重によって区別されている。このような規定から、権利義務の内容や刑の軽重とそれが実現されないまま経過した期間の長短との比較衡量が看取される。
法的な権利義務は本来当然に実現されるべきである。しかし、本来の権利義務が実現されないままの不当な状態でも、それが長期間継続すると、人々はその事実状態を前提として行動し、その事実状態を前提として他の人々と様々な関係を取り結ぶ。そのような状況で本来の権利義務を実現しようとすると、長期間継続した事実状態に基づいて形成された現存の人間関係・生活状態を、突如として破壊することになる。
それでも本来の権利義務を実現するべきだ、ということは、勿論ある。身内から犯罪者が出て一家全員破滅という事態は珍しくもない。しかし、事件直後ではなく長期間経過後になると、今更そこまでするべきではない、と考えられる場合もあり得る。この考えを是認するなら、「現存の諸関係を破壊してでも実現するべき権利義務なのか」という判断を要することになる。迅速処理を要する場面では、権利が比較的短期間で時効により消滅する。重い罪・重い刑なら現存の諸関係を破壊することになっても訴追・執行しなければならないが、軽い罪・軽い刑なら現存の諸関係の方を優先させて訴追・執行を断念する。権利義務の重みと時の重みとの比較衡量である。この比較衡量に基づいて社会的安定を図るのが、時効制度なのである。
勿論、法律上の諸制度を批判することは自由であり、時効制度廃止論も立法論として成立可能である。しかし、制度の趣旨に関する誤解があると、適切な議論にならない。
刑事において、「被害者や遺族に時効はない」との言葉がしばしば発せられる。それは正しい。無関係な他人や加害者・債務者は忘れても、被害者・債権者やその遺族は忘れないことが多い。
しかし、これを時効制度批判の根拠にすると、論点齟齬に陥る。このブログで過去に述べたように、刑罰は被害者や遺族のための復讐代行制度ではない。被害者の権利として犯人処罰を論じると、真に必要な被害者支援を失念させて犯人死亡事案の被害者を無視するだけでなく、刑事法の歪曲をも生じさせる。被害者や遺族の意向を根拠とする公訴時効廃止論も、その一例である。
犯人が如何に悪辣な行為をしたか、被害者が如何に悲惨な目に遭ったか、という事実を公的に確認することは、被害者支援の一環として重要事項である。刑事被告事件裁判が行われないためにこのような公的確認が行われないという状態は、被害者支援に欠ける。しかし、それは公訴時効完成事案だけではない。公訴時効未完成でも、犯人が死亡すれば刑事被告事件判決は宣告されないから、犯罪や被害の内容・程度を公的に確認する機会は失われる。この点で、犯人死亡事案の被害者は公訴時効完成事案の被害者と同じ状態にある。
公訴時効廃止をかかる状態の解消手段と位置付ける主張は、同じ状態にある犯人死亡事案の被害者を無視している。被害者支援策は、公訴時効完成事案にも犯人死亡事案にも対応できるものでなければならない。
では、公訴時効廃止と共に、犯人死亡事案でも刑事被告事件裁判を可能にするべきなのか。再審は被告人が死亡しても遂行されるが、それは誤って犯人とされた人の雪冤を目的とする制度だからである。通常手続でそのような文字通りの「被告人抜き裁判」は刑事被告事件裁判にならない。刑事被告事件裁判は「この被告人をどうするべきか」を論題とする制度だから、論題たる被告人がいなければ無意味であると共に、被害者を少なくとも直接的には論題とするものではない。だから、「この被害者のためにどうするべきか」を論題とするなら、刑事被告事件裁判とは別の制度として、純粋に被害者支援のための制度を構築するべきなのである。
そして、公訴時効を廃止しても、犯人処罰は保証されない。15年間捜査して公訴提起できなかった事件が更に30年を経て被疑者・証拠の確保に至ることは、ほぼ期待不可能である。150年を経て奇跡的に犯人が特定できても、終局は被疑者死亡による不起訴である。被疑事件終局がなければ永久に被疑事件であり続けるから、200年前の殺人事件に関する捜査もあり得ることになる。しかし、関係者全員死亡が明白な昔の事件を被疑事件として捜査することは、現実に行われるとは考え難く、刑事司法の趣旨から外れる。故に、被疑事件を閉じることなく永久に放置するか、人間の生命の限界を超えた頃に氏名不詳被疑者死亡と判断して終局にするか、どちらかしかない。いずれにしても刑事司法完遂にならない。例えば崇峻天皇暗殺事件の真相解明は、今上天皇陛下の御要望があっても、刑事司法ではなく歴史学に適する事項である。
刑事司法の目標が犯人処罰である限り、公訴時効の延長は制度趣旨の範囲に留まり得るが、廃止は無意味・矛盾である。詳論は省略するが、公訴時効廃止は刑事司法完遂よりも「永久に許さない」旨の態度表明という政治的色彩の方が濃い。
公訴時効に限らず、時効制度をどうするかは、本来の権利義務を長期間経過後でも実現できるようにすることが、誰に如何なる利益をもたらすか、誰に如何なる損失をもたらすか、という点を熟慮して決するべき事柄である。